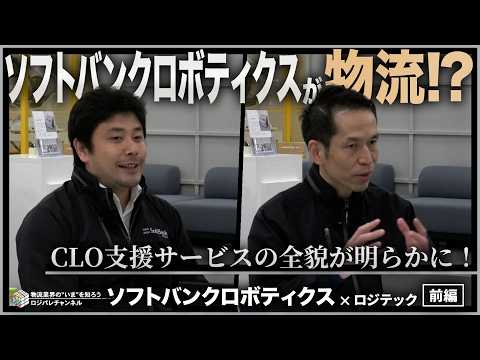各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
- 2025年10月1日から外免切替を全国一律で厳格化:住民票の写し必須、学科は50問で正答率9割、実技の確認・減点基準も強化(新規取得に準拠)。
- 観光・短期滞在者は切替不可に──候補者母集団が縮小し、合格までの再受験・研修が増えて稼働までのリードタイムが長期化。
- 国の方針は「育成前提」へ(育成就労→特定技能へ接続)。前提は日本の運転免許取得で、採用は即戦力頼みから育成型モデルへの転換が不可避。
ドライバー不足を埋める切り札だった外免切替
「人手が足りない」。どこの経営者に聞いても、もはや決まり文句のように出てくる言葉です。とりわけ物流業界では、ドライバー不足が慢性的な課題として横たわっています。その穴を埋める存在として、ここ数年注目されてきたのが外国人材です。実際に、海外で運転経験を積んだ人が日本で働くために「外国の運転免許証から日本の運転免許証への切替え手続き(通称:外免切替)」を行うケースは年々増加していました。
しかし、2025年10月1日からこの外免切替制度が大きく変わり、これまでに比べて一気にハードルが高くなりました。採用や現場運用にどう影響するのか──業界の関心が集まります。
制度改正の背景にある「炎上」と安全性の議論
そもそも、なぜ制度が厳しくなったのか。きっかけは、SNSや一部メディアで話題になった「ホテル住所で外免切替ができる」という事例でした。短期滞在の旅行者が、あたかも居住者のように免許を取得できてしまう。この“抜け穴”に世間の批判が集中し、安全性への懸念が一気に噴き出しました。
外免切替の件数は増加を続け、事故や違反のニュースと重なって「このままでは危ない」との声が強まりました。警察庁はついに制度見直しに踏み切り、2025年10月から全国一律で新ルールがスタートしたのです。
何が変わったのか?三つのポイント
今回の改正で特に大きな変更点は三つです。
三つの大きなポイント
- 住所要件の厳格化
住民票の写しが必須になり、観光ビザや短期滞在者は切替できなくなりました。いわゆる「ホテル住所問題」に明確な歯止めがかかった形です。 - 学科試験の難化
これまではイラスト中心の10問で7割正解すれば通過できましたが、今後は50問出題、9割正解で合格。文章理解力が求められる試験に変わり、“勉強なしの一発合格”は現実的に難しくなります。 - 実技試験の厳格化
横断歩道通過の確認など課題が増え、合図や右左折の不備に対する減点も厳しくなりました。事実上、日本で新たに免許を取るのと同等の水準に。
ドライバー採用に直撃するインパクト
物流業界にとって、これが何を意味するのか。端的に言えば「採用の歩留まりが下がる」ということです。
これまでなら、採用内定後に外免切替を経て、比較的スムーズにトラックドライバーとして現場に立てるケースも多かった。しかし今後は、学科・技能ともに難関化し、合格までの再受験や研修期間が長くなるのは避けられません。
さらに、住民票が必要になるため、短期滞在者はそもそも候補者から外れます。つまり、採用母集団そのものが縮小するのです。
「即戦力」から「育成前提」へ
かつて外免切替は、外国人ドライバーを短期間で“即戦力化”する近道でした。しかし今回の改正で、学科・技能は新規取得並みに厳しくなり、住民票がなければ申請もできません。採用から稼働までの時間は格段に長くなります。
さらに制度全体も「育成前提」にシフトしています。2024年には技能実習に代わる「育成就労」が創設され、目的を人材育成に置き、修了後は「特定技能」への移行を見据える仕組みに変わりました。また、特定技能の対象に自動車運送業が加わり、外国人ドライバーを公式に受け入れる道も開かれています。ただし、その前提は日本の運転免許取得です。
つまり外免切替の厳格化は、単なる制度改正ではなく「育てて活かす」という国の方針と軌をひとつにしています。物流企業に求められるのは、即戦力頼みから脱却し、「採用 → 教育 → 免許取得 → 配置」というプロセスを織り込んだ人材活用モデルへの転換です。
対応策はあるのか?
では、物流企業はどう動くべきでしょうか。鍵になるのは、前章で述べた「育成を前提とした人材活用」です。
まず、即戦力が見込めるのは、すでに日本の免許を持つ在留者です。こちらは優先的に採用し、現場の即戦力として活用するのが現実的でしょう。
一方、外免を持って来日する人材については、教育投資を前提に考える必要があります。免許を切り替えるまでの間は庫内作業や補助業務に従事してもらい、学科・技能の学習を並行して進める。合格後にドライバーへ登用する二段階モデルが、新しいスタンダードになります。
その上で重要になるのが「育成を支える仕組みづくり」です。教習所や研修機関と連携し、外国人向けの合格支援パッケージを整える。AI教材やeラーニング、多言語対応の模擬試験を活用すれば、学習環境を効率よく提供できます。
こうした取り組みは一企業単位では限界もあるため、業界団体や協議会と連動して教育資源をシェアすることも現実的です。単発の採用で終わらせず、長期的に人材を育てる体制こそが、これからの物流企業の競争力を左右します。

まとめ
外免切替の厳格化は、一見すると物流業界にとって逆風のように映ります。しかし、裏を返せば「安全性を担保した外国人材の採用が進む」ということでもあります。
即戦力の近道は閉ざされたかもしれませんが、計画的な育成と支援を行えば、安定して人材を活かせる土壌を作ることは可能です。これを機に、「外国人材をどう受け入れ、どう育てるか」を本気で考えることが、物流業界の未来を支える力になるのではないでしょうか。