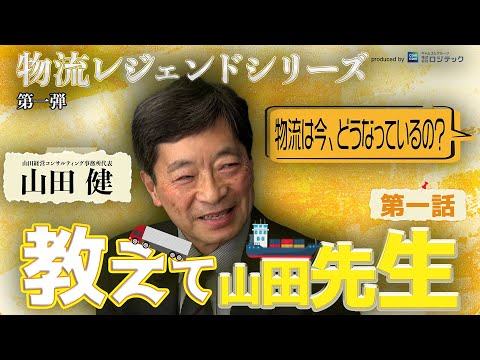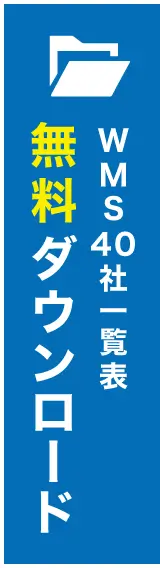目次
- 許可は5年更新制に移行。原価割れは財務悪化を招き、更新審査で不許可(実質免許剥奪)のリスクを高める。
- 荷主の過度な値下げ要求や不適切発注は、働きかけ・勧告等の対象に。発注姿勢そのものがコンプライアンスリスク。
- 対応は適正運賃の実装:原価の可視化共有/共同配送等の効率化/燃料サーチャージ/契約の文書化/定期見直しを仕組み化。
「もう少し単価を下げられませんか?」
その一言が、取引停止や監査対象の引き金になる——そんな時代が、もう来ています。
2024年の法改正により、運送業では5年ごとの許可更新制が導入されました。更新時には法令順守や安全管理、財務の健全性が厳格にチェックされ、原価割れ契約による法令違反は更新不可の原因となります。さらに、不適切な発注を行った荷主にも国交省から改善指導が入る時代になりました。
本記事では、物流企業・荷主双方の立場から「なぜ値下げ要求がリスクになるのか」「適正運賃をどう実現するか」を実務視点で解説します。
法改正で何が変わったのか──更新制度の実務インパクト

2024年の改正貨物自動車運送事業法により、運送業に5年ごとの許可更新制度が導入されました。従来の「永久許可」制度は廃止され、今後は定期的な審査をクリアしなければ事業継続できません。
更新審査の3つの柱
更新審査では、主に次の3つの観点から事業者の適格性が判断されます。
まず法令順守。労働時間管理・点呼記録・運行管理の適正性が細かくチェックされます。
次に安全体制。事故率・車両整備状況・安全投資の実績など、安全への取り組み姿勢が問われます。
そして財務健全性。自己資本比率・利益率・キャッシュフローといった経営指標が基準を満たしているかが審査されます。
ここで注目すべきは、原価割れ契約が財務悪化→更新不可という連鎖を生む点です。国交省は「適正運賃の収受に向けた取り組み状況」も審査項目に含める方針を示しており、値下げ圧力に屈した取引履歴そのものが評価を下げる要因になります。
荷主側にとっても他人事ではありません。過度な値下げ要求や短納期発注が運送会社の法令違反を誘発した場合、貨物自動車運送事業法第64条に基づき荷主への働きかけや勧告が行われます。つまり、発注姿勢そのものがコンプライアンスリスクになる時代です。
原価割れ契約が引き起こす”3つの経営リスク”

物流業界では、燃料費高騰・人件費上昇により、トラック1台あたりの月間固定費は平均80万円超といわれています。これを下回る単価での受注は、経営を蝕む"不良債権"と化します。
1. 安全投資の削減→事故リスク増大
整備費や車両更新費を削ることで、車両トラブルや重大事故のリスクが高まります。結果として、荷主は納期遅延・荷物破損・企業イメージ低下というダメージを受けることになるでしょう。
2. 労務違反の常態化→突然の取引停止
人件費を抑えるため拘束時間超過や休息不足が常態化し、労基署の監査で事業停止処分を受けるケースが増えています。主要協力会社が突然使えなくなる——こうした状況は、荷主にとって最大の物流リスクといえます。
3. 経営破綻による物流崩壊
2023年の運送業倒産件数は過去最多を更新しました。主力運送会社の破綻は、代替輸送の確保・運賃急騰・顧客信用の失墜という三重苦を招きます。
「安く発注したはずが、結果的に高くつく」——これが原価割れ契約の本質です。
荷主が注意すべき”発注行為”のグレーゾーン
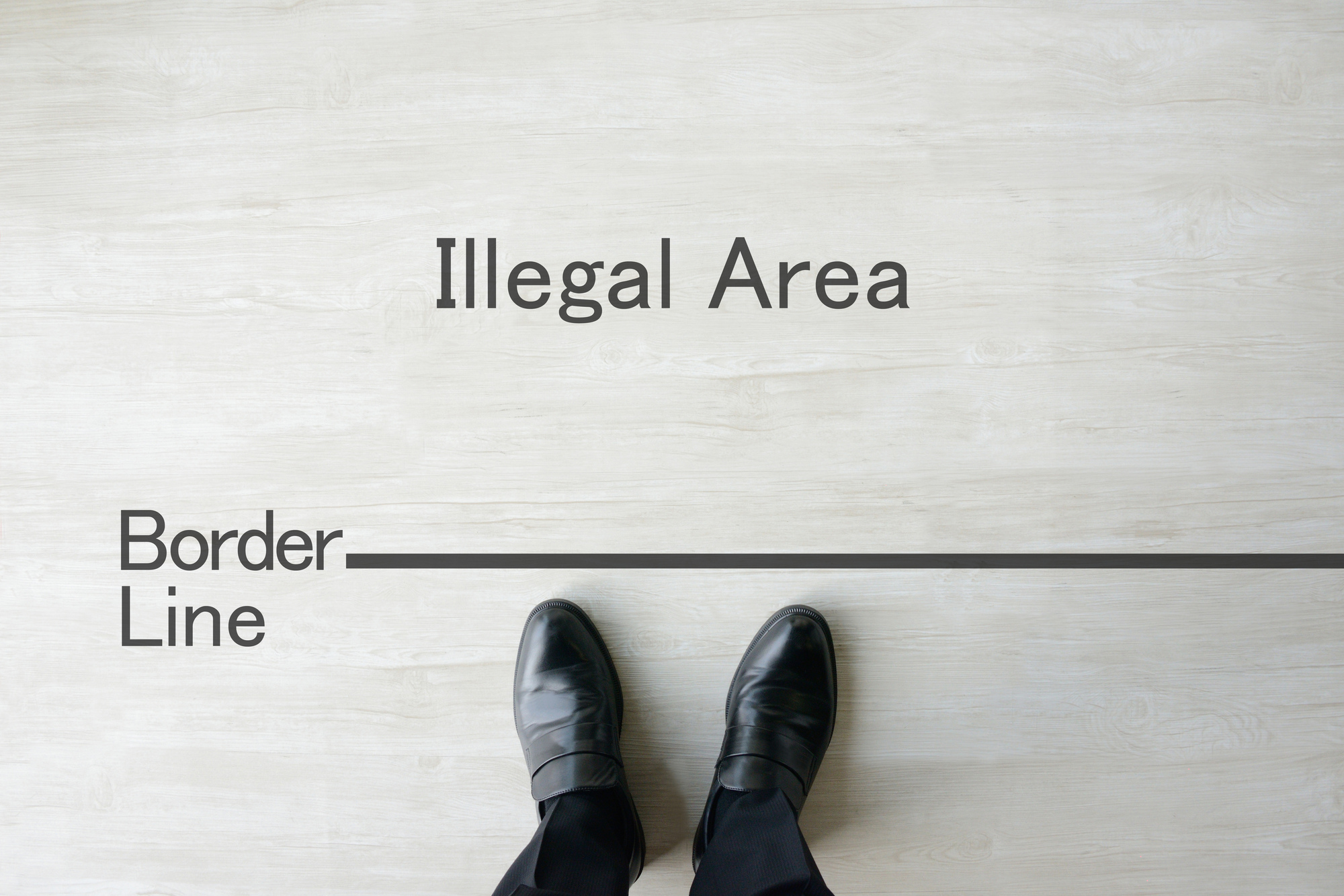
国交省は現在、以下のような荷主の不適切行為を監視しています。
たとえば、以下のような行為です。
- 相見積もりを引き合いに出した一方的な値下げ要求
- 作業量増加・待機時間発生を織り込まない据え置き契約
- 燃料サーチャージや高速代の負担拒否
- 支払サイトの一方的延長(60日超など)
- 契約書なし・口頭発注の常態化
こうした行為は、運送会社を法令違反へ追い込む構造的要因と認定され、荷主名の公表・取引改善命令の対象となる可能性があります。「業界慣習だから」は通用しません。
発注側もコンプライアンスの当事者——この認識転換が、いま求められています。
適正運賃を実現する”5つの実務アクション”

では、どう価格交渉を変えるべきか。物流現場で実践されている5つのアプローチを紹介します。
① コスト構造の可視化共有
燃料費・人件費・車両償却費を明示した原価表をベースに対話します。「なぜこの価格か」の根拠を共有することで、値下げ余地の有無を客観的に判断できるようになります。
② 共同配送・混載による効率化提案
単価交渉ではなく、積載率向上・共同配送・リードタイム調整など、双方の利益を生む構造改善を交渉のテーブルに載せます。
③ 燃料サーチャージ制の導入
変動費を固定価格に含めず、燃料価格連動で調整する仕組みを契約化します。リスクの適正配分が長期安定取引の基盤になります。
④ 契約書・覚書の文書化徹底
運賃・附帯作業・支払条件を明文化し、変更履歴を残します。後々の「言った言わない」トラブルを防ぎ、透明性を担保します。
⑤ 定期的な運賃見直しの仕組み化
年1回など、定期的に原価変動を反映する見直し機会を設定しましょう。「据え置き前提」から「適正価格の継続確認」へと発想を転換します。
これらは単なる値上げ交渉ではなく、持続可能な物流パートナーシップを築く投資です。
法令順守が最強のコスト対策になる時代

ここまで見てきたように、物流を巡る環境は大きく変わりました。
許可更新制により、運送会社の法令順守が"生き残り条件"に。原価割れ契約は安全・労務・財務の三重リスクを生み、荷主にも跳ね返ってきます。荷主の不適切発注には国交省の監視・指導が及びます。適正運賃の実現は、コスト増ではなく"リスクヘッジ投資"なのです。そして、透明性・対話・構造改善が、新時代の取引の基盤となります。
法改正によって、物流は"価格競争"から"信頼競争"へと軸足を移しました。
安さを競うより、持続性を築く取引へ。
それが、法令を守り、企業を守り、物流を守る最も確実な道だといえるでしょう。