PICKUP

SERIES
シリーズ別記事
物流現場取材シリーズ
様々な現場で活躍する物流業界の「現在」をロジテック社長の川村が取材に行く

物流現場取材シリーズ【19】 物流コンサルティングがリードするDXの未来像とその実現方法
2024.09.10
物流系イベントレポート
物流業界の大規模展示会・フォーラム・その他イベントの取材レポートをお届けします

今、「第二回物流DX会議」を開催する狙いは?主催者に聞いてみた物流業界の活性化戦略
2024.10.02

【ジャパントラックショー2024レポート】
トラック業界の最前線
2024.06.17

【第5回関西物流展レポート】
未来を形作るイノベーションの現場
2024.05.14








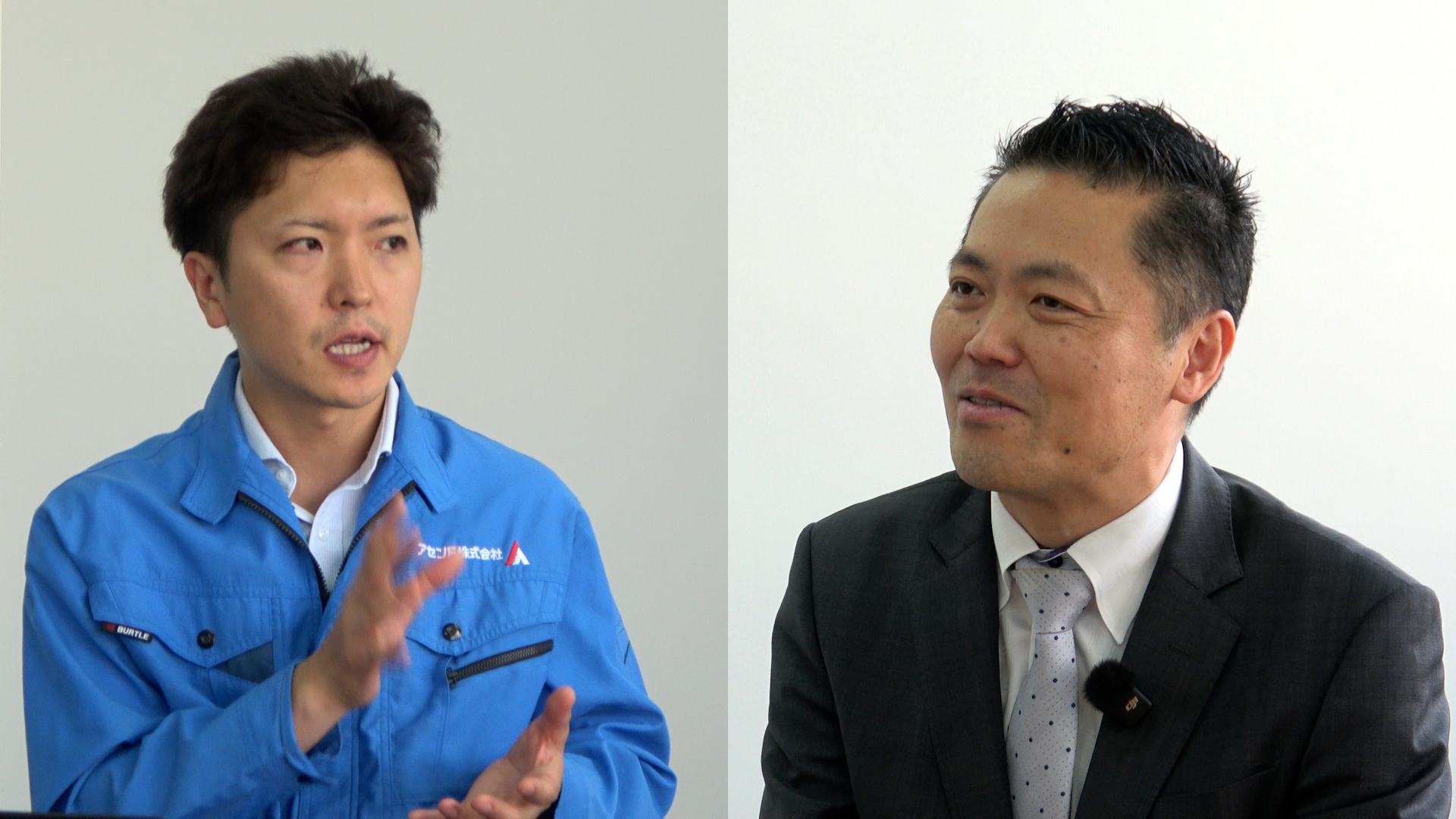





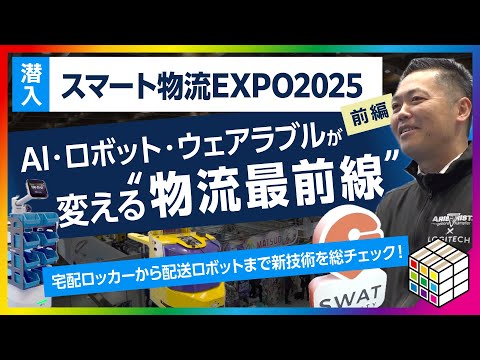
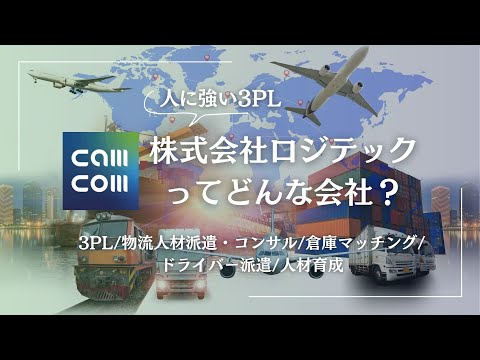
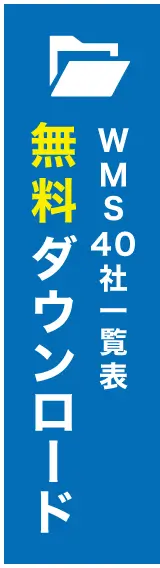
10分でわかりやすく解説
基本から最新情報まで物流業界にまつわる話題・専門知識をわかりやすく解説します
ハイキューブコンテナとは?10分で解説
テアウェイトとは?10分で解説
コンテナシールとは?10分で解説
ネットウェイトとは?10分で解説