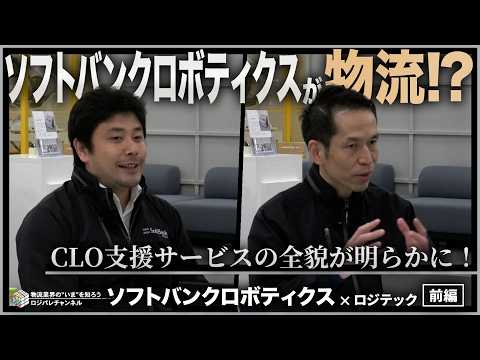各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
近年、EC市場の拡大や多頻度小口配送の増加を背景に、物流業界では迅速な出荷対応が求められてきています。そのような中で、在庫を持たずにその日のうちに仕分け・出荷を行う「スルー型センター」の重要性が高まっています。
この記事では、物流に関する知識がない方にも理解しやすいよう、スルー型センターの仕組みやメリット、活用事例、さらには今後の展望までを解説します。
スルー型センターの基本構造とは?

はじめに、スルー型センターはどのような仕組みで動いているのでしょうか。ここでは基本構造について解説します。
スルー型センターとは?
スルー型センターとは、卸業者などから納品された商品を在庫として保管せず、当日中に仕分け・出荷する物流拠点です。一般的な倉庫や在庫型物流センターとは異なり、商品を一時的に滞留させることなく、できる限りスムーズに流通させることを目的としています。
そのため「通過型」「通過型物流センター」などと呼ばれることもあります。
主な業務フロー
スルー型センターにおける基本的な業務の流れは以下の通りです。これら一連の流れを、可能な限り短時間で行うことがスルー型センターの大きな特徴です。
- 納品受付:卸業者などから商品が納品される
- 検品・一時配置:納品内容の確認と、仮置き場での一時保管(短時間)
- 仕分け作業:出荷先や配送ルートに応じて商品を振り分け
- 出荷・配送:その日のうちに配送業者に引き渡し、顧客へ出荷
必要な設備とシステム
スルー型センターでは、短時間で大量の商品をさばくため、以下のような設備とシステムの整備が必要不可欠です。効率を重視させるため、作業の自動化と作業導線の工夫が求められています。
- 高速仕分け機器:自動仕分けラインやコンベア、ハンディ端末など
- 効率的な動線設計:一筆書き動線を意識したレイアウトで無駄な移動を排除
- 情報連携システム(WMSなど):受注情報・納品情報をリアルタイムで連携し、作業指示や進捗を一元管理
スルー型センターとクロスドッキングシステムの違い
スルー型センターを説明する際に混同されがちなのが、クロスドッキングシステムです。
どちらも「在庫を持たずに商品を速やかに出荷する」という点では似ていますが、対象とする概念の範囲に違いがあります。
スルー型センターとは、通過型の物流を前提とした拠点の形態を指し、入荷から出荷までを可能な限り短時間で処理することを目的とした施設です。在庫保管スペースを最小限にし、商品が滞留せず流れる仕組みが重視されます。
一方のクロスドッキングシステムは、そのスルー型センター内などで実施される具体的なオペレーションのひとつです。入荷した商品を倉庫に格納することなく、すぐに仕分けして出荷先ごとに積み替える工程を指します。
スルー型センター=通過型物流の拠点
クロスドッキング=その中で行われる仕分け・積み替えの作業
という関係性にあり、必ずしもセットで使われるわけではありません。スルー型センターがクロスドッキング以外の機能を持つ場合もあれば、クロスドッキングが別の物流拠点で実施されることもあります。
スルー型センターの導入メリット
スルー型センターを導入することで、様々なメリットがあります。ここでは4つのメリットについて解説します。
1. 在庫コストの削減
スルー型センターでは、商品を長期間保管しないため、在庫に関わるコストを大幅に削減できます。たとえば、倉庫スペースの賃料や光熱費、保管用棚やパレットといった設備投資、さらに定期的な棚卸しや在庫差異のチェックにかかる人件費などが抑えられます。
これにより、物流コスト全体の最適化が実現できます。
2. 在庫リスクの軽減
在庫を保有しないことは、単なるコスト削減にとどまりません。保管時間が短縮されることで、商品の破損、盗難、品質劣化といった在庫リスクが軽減されます。
特に賞味期限や消費期限のある食品、温度・湿度に敏感な化粧品や医薬品などには大きなメリットがあります。
また、需要変動の影響を受けにくくなり、売れ残りによるロスを回避できる点もポイントです。
3. リードタイムの短縮
納品から出荷までを1日以内に完了できることで、注文から納品までのリードタイムを短縮できます。これは、消費者に迅速な商品提供が求められる現代において大きな競争優位性につながります。
特に、BtoCビジネスにおける「翌日配送」「当日配送」のニーズにも対応しやすくなります。
4. フレキシブルな運用
スルー型センターは、在庫を持たないため、繁忙期や突発的な需要の増加にも柔軟に対応できる構造になっています。
人員や仕分けラインの増設など、状況に応じた即応性が高く、イベント対応や短期キャンペーンにも適しています。また、拠点の設計次第では、多品種少量の取り扱いにも対応可能です。
スルー型センター導入時の注意点
一方でスルー型センターは、どんな貨物でも適用できるわけではありません。ここでは、導入時の注意点を紹介します。
1. 業務プロセスの設計
スルー型センターでは、作業工程のスピードと正確性が求められるため、業務プロセスの設計が最も重要なポイントです。入荷から出荷までの流れを徹底的に可視化し、作業手順を標準化することで、業務の属人化を防ぎます。
また、作業のボトルネックを見つけ出し、レイアウトや人員配置の見直しを行うことで、業務効率が格段に向上します。
2. 人材教育とオペレーション
作業の大半を人手に頼る場合も多いため、作業員のスキルと知識の水準が安定運用に直結します。特に仕分け作業や検品などは、単純なようでいてヒューマンエラーが発生しやすい工程です。
新人教育マニュアルの整備、OJTの強化、定期的なリフレッシュ教育により、一定の品質を保つことが重要です。
また、作業ミスを早期に検知するためのダブルチェック体制やトレーサビリティの導入も効果的です。
3. システム連携とデータ精度
スルー型センターでは、受注・入荷・出荷といった情報をリアルタイムで連携させることが前提となります。そのため、各業務システム(WMS、TMS、ERPなど)とのシームレスな連携が不可欠です。
また、誤出荷を防ぐには、バーコードやRFIDによる商品識別やスキャンによる実績管理など、データ精度を高める仕組みが求められます。システム障害に備えたバックアップ体制も準備しておくと安心です。
4. 繁忙期の対応力
季節商材やキャンペーン商品を扱う場合、一定期間に荷量が急増することがあります。このような繁忙期に対応するためには、臨時スタッフの確保や作業ラインの一時的な増強、夜間や休日の運用体制など、柔軟なリソース配分が不可欠です。
事前に予測データをもとにした荷量シミュレーションを行い、ピークに備えた準備を整えておくことが、スムーズなセンター運営につながります。
スルー型センターの導入事例
スルー型センターはどのような場面で活用されているのでしょうか?ここでは導入事例を紹介します。
1. ECビジネスにおける活用
ネット通販を手がけるメーカーや小売事業者では、注文を受けてから迅速に商品を出荷する体制が不可欠です。スルー型センターを導入することで、受注後のピッキングや梱包、出荷までを効率よく行うことができます。
たとえば大手アパレルメーカーでは、消費者の注文データをリアルタイムで連携し、センター内で即座に仕分け・出荷を行うことで、「翌日配送」「当日配送」に対応しています。
2. 流通業者との連携
卸業者が複数の小売店に商品を供給する場合、スルー型センターを中継地点とすることで、拠点での保管作業を省きつつ確実に配送できます。在庫管理をアウトソーシングしたい流通業者にも適しており、センターでの仕分けによって各店舗ごとの仕入れ数量に応じたピッキングが可能になります。
これにより、配送車両の積載効率も向上し、店舗への納品もスムーズになります。
3. 繁忙期・イベント対応
季節商材(例:バレンタインデー、年末商戦、花火大会など)やイベント関連商品など、一時的に出荷量が急増するケースでも、スルー型センターは短期的な大量処理に対応しやすい構造です。
スルー型センターの最新トレンドと今後の展望

スルー型センターの活用は単なる「在庫を持たない拠点」にとどまらず、技術革新や都市型物流との融合によって大きく進化しています。ここでは、スルー型センターがどのように変化しているか、そして今後どのような展望があるのかを詳しく解説します。
1. 自動化・スマート化による省人化の加速
人手不足や高齢化が進むなか、スルー型センターの自動化はますます重要性を増しています。仕分けロボットや自動搬送装置(AGV)、AIカメラによる検品作業の自動判別など、先進技術を活用することで作業精度を高めつつ、少人数での運用が可能になります。
これにより、人的ミスの削減と同時に、安定的なサービス提供が実現できます。また、デジタルツインやIoTセンサーによる作業状況の可視化も、リアルタイムの改善活動に役立っています。
2. マイクロフルフィルメントとの統合
都市部では「マイクロフルフィルメントセンター(MFC)」との融合が進んでいます。これは、小規模かつ消費地に近い拠点で即日配送やピックアップ対応を行う施設です。
スルー型センターが都市近郊に点在することで、配送リードタイムをさらに短縮し、需要の変化にも柔軟に対応可能になります。コンビニやスーパーのバックヤードを活用する事例もあり、店舗と物流の垣根を越えた新たなオペレーションが展開されています。
3. 持続可能な物流の実現
環境への配慮も、スルー型センターの進化において欠かせない要素となっています。再利用可能な通い箱や緩衝材の導入、LED照明やソーラー発電などのエネルギー効率化、配送ルートの最適化によるCO2排出削減など、サステナブルな取り組みが進行中です。
これにより、物流活動そのものを企業の環境戦略と連動させる動きが加速しています。
まとめ
スルー型センターは、現代のスピード重視・在庫リスク最小化の物流ニーズに適した拠点として、幅広い業種で導入が進んでいます。導入には緻密な業務設計とIT連携、柔軟な運用体制が求められますが、正しく活用すればリードタイムの短縮、在庫コストの削減、顧客満足度の向上といった多くのメリットが得られます。
今後はAI・IoTの技術革新や環境対応の進展により、よりスマートで持続可能なスルー型センターが求められていくでしょう。物流戦略を考えるうえで、今まさに注目すべき選択肢といえます。