
目次

物流業界に精通した経営コンサルタントとして、長年にわたり運送会社の経営改善や業務効率化に取り組む山田経営コンサルティング事務所。10年以上前からドライバー不足の深刻化に警鐘を鳴らし続け、2024年問題が話題となる遥か以前から業界の構造的課題に向き合ってきました。
今回は、物流業界の「現在」を深く掘り下げ、その課題の「過去」の根源を解き明かし、そして「未来」への具体的な変革の道筋を示す羅針盤となるべく、山田経営コンサルティング事務所代表の山田さま(以下、敬称略)に、業界が直面する本質的な課題と解決への道筋について、ざっくばらんにお話をうかがいました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。
2024年問題の本質とは何か
川村:まず、2024年問題について伺いたいと思います。世間では時間外労働規制の問題として語られることが多いですが、山田さんはどのように捉えていらっしゃいますか?
山田:2024年問題自体は大した問題じゃないと私は思っています。これは別に今に始まった話ではなくて、ドライバーになる人が減っているというこの問題が決定的に問題です。ここをなんとかしないと単に時間改正がどうしたこうしたの話ではないんです。
川村:なるほど。つまり働き方改革だけで終わる話ではないということでしょうか。
山田:そうです。業界全体の形を変えていかないといけない。例えば共同配送だとかモーダルシフトとかいろいろ出てきてはいるけど、決定的な問題の緩和にはつながらないんです。もう規模感の問題で、圧倒的な物量に対して、じゃあ鉄道で運ぼうと言っても全然キャパないですから。海上も同じです。
川村:過労死ラインの問題についても教えてください。960時間という数字をどう見ていますか?
山田:これがまずすごく異常な数字なんです。一般の人たちは720時間ですから。960時間ってことは月80時間という過労死ラインなんです。にもかかわらず、それでも足りないと言っているわけです。ということは、今までどれだけオーバーしてたかってことなんです。
川村:構造的な問題ということでしょうか?
山田:まさにそこです。それをやらないと回らないというか、荷主側の部分がそうなっちゃってるんです。みんなやりたくてやってるわけじゃなくて、そういう時間帯でやらないと、物が運べない仕組みができちゃってるんです。端的な例で言うと、東京港のコンテナヤード。コンテナを引っ張ってくる仕事があるんですが、少なくとも5〜6年前から東京港のコンテナヤードがキャパオーバーしてるんです。ヤードに入るのに3〜4時間待ちっていうのが、もう当たり前の世界になってしまってるんです。ひどい時は7~8時間で、これが全く解消してないんです。
川村:待機時間も労働時間に含まれるわけですから、これは深刻な問題ですね。
山田:そうです。少なくともその物流事業者側ではどうしようもないお話ですし、今の東京港の問題なんかは、誰がそういう仕組みにしてるって別に当事者がいるわけじゃないんです。完全にキャパオーバーの物量が集まってしまってるということなのでどうしようもないんですよ。
慢性的な人手不足の現状
川村:人手不足の問題についても深刻だと思うのですが、特にドライバー領域はいかがでしょうか?
山田:物流業界、特にドライバー領域における深刻な人手不足は、人口減少に加え、業界の不人気が相まって、顕在化している状況です。特に大型ドライバーって、今もう20代・30代の人はほとんどいないんです。ほぼ40代から60代だけなんです。その人たちは今後10年単位でいなくなりますから。
川村:それは衝撃的な数字ですね。
山田:2001年から20年ぐらいで7割近く減ってるんです。若い人がもう免許を取らないんです。そもそも普通免許もあまり取らないじゃないですか。それに加えて大型を取る方が本当にいなくなったから、長距離ドライバーももちろんいなくなっちゃうし、近距離だって大型ドライバーが必要なケースはかなりありますんで、ここが間違いなく動かなくなっちゃうんです。
川村:これはもう2024年問題とは全く関係なく進行している構造的な問題ということですね。
山田:そうです。もう構造的な問題です。今の20代の人たちがカバーできるかって言ったら、全くできない。この人たちが増えるかと言ったら残念ながら増える見込みもないじゃないですか。そう考えたら、多分日本ではリソースが全く回らなくなる。もうあとは女性なのか外国人なのかっていうことになるじゃないですか。
運行効率と経営の課題

川村:運送会社の経営面での課題についてはいかがでしょうか?
山田:実際見てると、運行効率の悪さやマネジメントの問題はすごくあります。結局トラックってのは運行効率がもう一番の指標なんです。いかに効率よく回すかっていう、そこを上げてくことで限られた運賃でも利益はもっと出せる余地があるんです。でも残念ながら運送会社さんを見ていてもそういう指標自体を取ってないです。
川村:データを取っていないということですか?
山田:だから本当に効率よく運行されてるかどうか評価ができないんです。だったら今の運賃が安いのか高いのかっていう評価もできないわけです。仮に運行効率が良くて、それでも利益が出ないなら、これは運賃が低いって話になるんだけど、残念ながらそこまで行かないんです。
川村:システム導入についてはどうお考えですか?
山田:第一歩はとにかくそういった数字をちゃんとまず取るようにしましょうよ、です。さらに数字を取るためには、TMSという運行管理システムみたいなものを入れざるを得ないです。そのような作業を手作業で一台一台行うわけにいかないですよね。そういう点ではやっぱりITの力を借りることは絶対必要だと思います。
川村:TMSの導入で皆さん悩まれることが多いようですが。
山田:皆さん難しいと思ってるけど、決してそんなことないです。選び方というよりは、基本はツールに合わせて仕事を変えなきゃいけません。自分に合わせたものを選ぶよりは、そもそも自分でやってるやり方が効率的かどうかわからないじゃないですか。もし非効率なやり方をしてるとしたら、非効率なやり方にシステムを合わせちゃうことになるから、何にもならない。やっぱりシステムのいいところは、ベストプラクティスが詰まっているところですから、それに合わせて仕事のやり方も全部変えていくっていうやり方をしないと、システムの効果は出ないです。
業界の慣習と変革への障壁
川村:物流2法の改正についてはどのように捉えていらっしゃいますか?
山田:法律が変わったからと言ってどうなのかな、という気は正直しています。というのは、今まで物流に関わる法律ってどんどん変わってるんです。でも実態が何も変わってなかったっていう場合がほとんどでして。例えば、トラックの運賃って1991年以前は認可運賃だったんです。認可運賃のタクシーもバスも電車もみんなそうだけど、それで運ばなきゃ本来法律違反です。
川村:しかし実態は違ったということですね。
山田:その頃からトラック運賃は認可運賃でありながら、実勢運賃だった。つまり荷主さんとの交渉で決まる運賃。法律があるにも関わらずそういう実態が今も全く変わってない。法律だけが変わってきたっていうのが実態なんです。
川村:その背景には何があるのでしょうか?
山田:私も正直、物流の営業やってて認可運賃だって意識したこと一度もないです。運賃っていうのはもう交渉で決まるものだと、やってる側が思ってるわけですから。そんなことを誰も意識してなくて、電話一本でやっちゃうっていう状況があります。
料金交渉と意識改革
川村:運送会社が料金交渉で苦労されているという話をよく聞きますが。
山田:やっぱり皆さんここで困っています。ただ言えるのは、これからもっと強気でやっていいんじゃないかなと。会社側に、何十年にもわたった値上げを言い出せないDNAのようなものがあると思うんです。そこはちょっと極端に言えばもう仕事がなくなってもいいぐらいのつもりで交渉する姿勢は必要だと思います。
川村:値上げには抵抗があるのも理解できますが。
山田:今やらなかったら、もうチャンスはないです。せっかく2024年問題と言ってみんなが関心を持ってくれてる今やらなかったら、次のチャンスはすぐには来ないです。もちろん根拠は必要だと思います。ただ上げてくれっていうんじゃなくて、当然運送の原価っていうのはあるし、ドライバーの賃金もあるわけですから。そういうことをきっちり押さえた中で、やっぱりちゃんとデータを持って交渉する必要があると思います。
人材確保と採用戦略
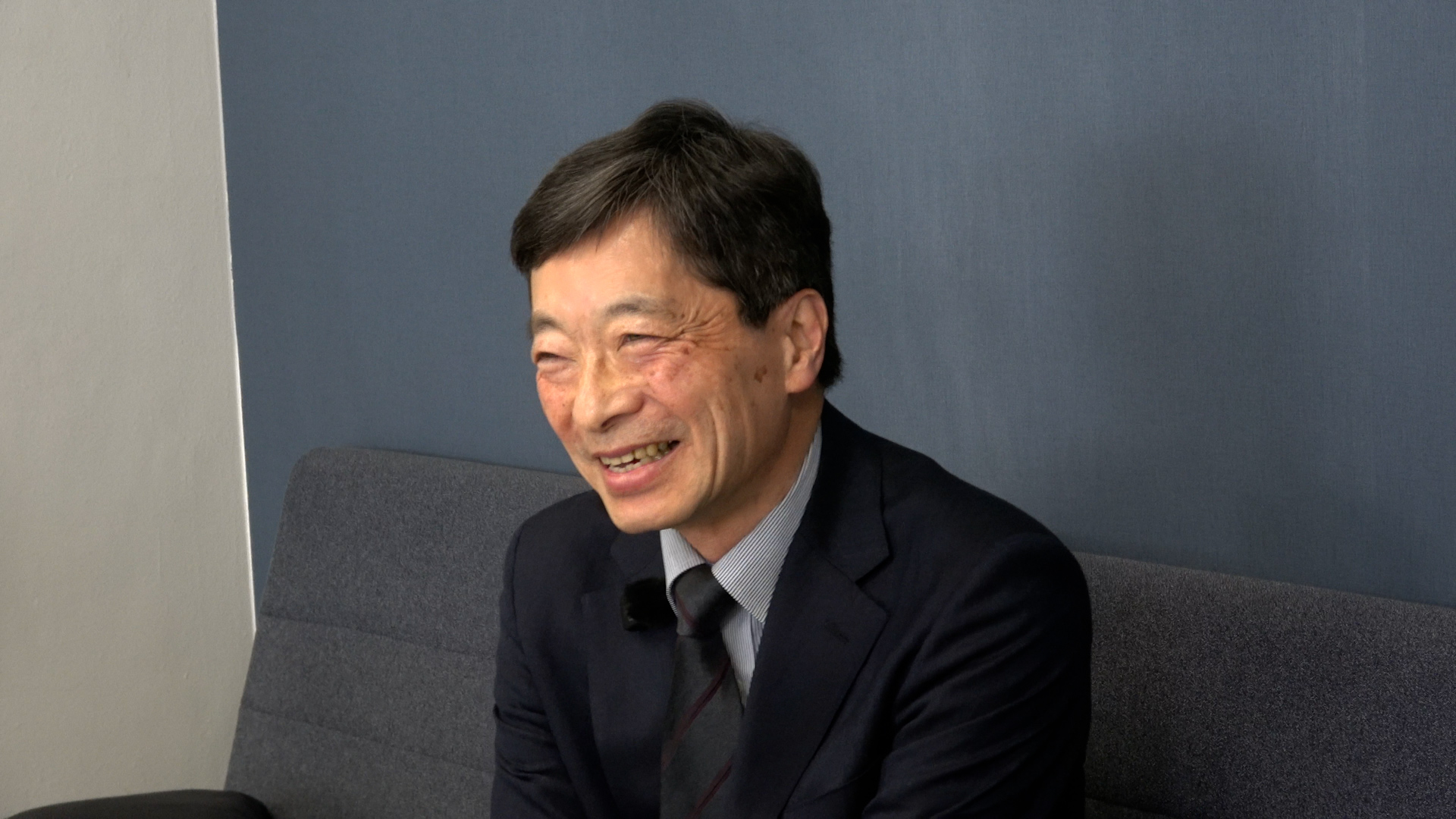
川村:採用についてはいかがでしょうか?良い取り組み事例などはありますか?
山田:そういう事例があれば私も苦労しないです(笑)。見てるとやっぱりコネクションで引っ張ってくる。今見てるところは、もちろん新卒なんか来ないから、別の運送会社から何らかのコネクションで採用してます。さっきのそのコンテナの話で思い出しましたけど、ポイントは労働時間です。比較的普通の労働時間で働けるところに人は来るように思います。
川村:労働時間の改善が重要ということですね。
山田:コンテナの話だと、3~4時間も待ち時間があるので、結構車の中に泊まってる人が多いんです。東京のあの辺りで1週間泊まって、土日に家に帰るみたいな。その状態だともうもたなくなって、もうちょっと普通の時間で働けるならと言って、来てくれたケースがあったんです。社長はすごく喜んでいました。こういうケースもあるんだなと。決して賃金がいいわけじゃないんです。ただもうそういう生活だと、とてももたないということで。
川村:賃金以外の要素も重要だということですね。
山田:もちろん賃金の話は大きいけど、それ以上にやっぱりコミュニケーションの問題とか評価の問題とか、その辺りを皆さんかなり不満に思ってます。長期で腰を据えようとしたら、お金以外のところをいかに充実させるかっていうのは、採用で優位に立つ方法です。
外国人材の活用について
川村:2025年から特定技能のドライバー、外国人ドライバーが解禁されますが、どう見ていますか?
山田:期待しています。2019年にこの制度ができてから、なんで物流が入ってないの?とずっと思ってましたから。介護の現場なんかはすでに入ってるわけです。ある意味介護より運転の方がまだ親和性はあるような気がします。介護ってコミュニケーション取らなきゃいけないけど、運送会社はそれほどお客さんと接する部分が多いわけじゃないじゃないですか。だとしたら、むしろドライバーの方が特定技能には向いてるような気がするんです。
川村:受け入れ側の懸念などはありますか?
山田:多分、運送会社の社長さんはそれを気にしてるでしょうね。交通マナーの問題は確かにあります。でも介護はいろんな意味で政府の補助があるじゃないですか、介護報酬という。この業界にはそういうものが全くないわけですから、不足という意味ではるかに深刻なはずなんです。だったら介護以上にやっぱりこの業界も受け入れる必要があると思います。
川村:ライフサポートなどの支援体制についてはいかがでしょうか?
山田:一回研究したことはありますけど、あまりにも規制が厳しすぎて。例えば下宿先でもなんでも全部決まってるんです。1人当たり何平米以上で、キッチンがどうしたこうしたって、そういうスペックが厳密に決められてて。そういうのを見ただけで、少なくとも中小企業の人は「こんなのとても」って思っちゃう。そういうところのサポートをやっていただければ、その負担はなくなるかと思います。特に中小の運送会社さんだったらそういうサポートはすごく助かると思います。
川村:時間的な猶予についてはいかがですか?
山田:もうのんきなことは言ってられない状況でしょってことなんです。おそらく、少なくともあと10年経ったら、みんないなくなっちゃいますから。その時には本当に運べなくなっちゃうんで、それまでに間違いなく必要になると思います。
物流業界の誤解と可能性
川村:物流業界への誤解についてはいかがですか?
山田:一般的に物流イコールトラック、イコール宅配ってこういう流れで、2024年問題が宅配の問題になっちゃうんですが、実はそういうところ以外の方がはるかに物流って多いわけで。物流って誤解されてる部分がものすごく多いです。
川村:社会的な意義についてはどうお考えですか?
山田:実際にこの世の中を完全に支えている仕事です。物流が止まったら、我々は一日足りとも生きていけない。そういう意味での社会的な意義はあります。あとは業務の改善については今まで全く手をつけていないところですから、やり方によっては、いくらでも変えられる余地はあると思います。
川村:業界の魅力を伝えることについては?
山田:業界に入ってみると思ったのが、めちゃくちゃ食わず嫌いだとかステレオタイプに捉えられてたところが多いなと。やったらめちゃくちゃ奥深いですし面白いじゃないですか。だから、ちゃんと説明したら興味を持ってくれると思うんですが、誰も手をつけてない。
ロジテックの役割と未来への取り組み

川村:システム導入などで我々がお手伝いできることはありますか?
山田:手前味噌になっちゃいますが、我々がちょっとお手伝いをさせてもらって、運送会社さんとベンダーさんの通訳みたいなことをしてやる必要はあると思っています。
川村:海外展開についても検討していますが。
山田:私が教えている流通経済大学のクラスの3分の1ぐらいがベトナム人です。留学生ばっかりです。結構優秀ですよ。
川村:日本に連れてくるだけじゃなくて、現地で雇って現地で働くとか、帰国した後の働き場所みたいな意味でも、海外拠点があると雇い方が変わるという発想もありますね。
山田:そういう取り組みは大きなビジネスチャンスになると思います。
変革への一歩を踏み出すために
川村:最後に、物流業界の未来についてメッセージをお願いします。
山田:我々の期待としては、ドライバーの待遇が上がっていくことで人が増えていくことを期待したいんです。物流業界が直面する課題は深刻ですが、同時に大きな変革のチャンスを迎えていると思います。
川村:経営者の皆さんへのメッセージは?
山田:経営者が「変わる」と決意し、行動を起こすことが未来を拓く鍵だと思います。強気の料金交渉、DXの推進、人材確保戦略、業界の意識改革。これらが重要になってきます。
川村:本日は貴重なお話をありがとうございました。物流は社会を支える重要なインフラであり、その価値を正しく評価し、持続可能な業界へと変革していく時が来ています。変革の時だからこそ、業界全体で力を合わせ、未来を拓く羅針盤として進んでいく必要があります。ロジテックも、その変革の道のりを共に歩むパートナーとして、皆様をサポートしてまいります。
企業プロフィール
会社名:山田経営コンサルティング事務所
本社所在地:東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
設立:2014年6月









