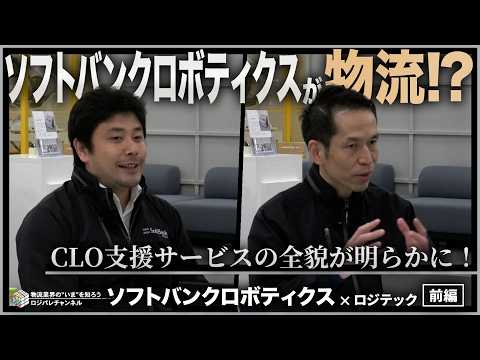各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
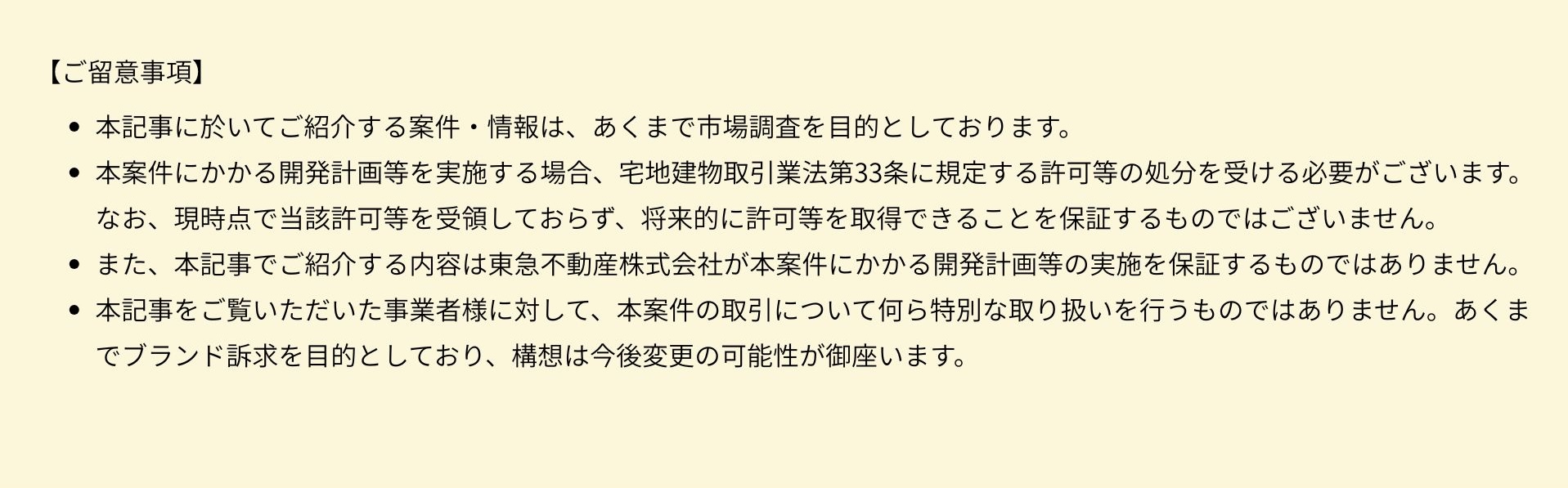
今回は、従来の物流施設開発の枠を超えた革新的な取り組みについて、東急不動産株式会社インフラ・インダストリー事業ユニット インダストリー事業本部 開発企画部 基幹産業拠点推進室 室長の石井拓也さま(以下、敬称略)に、産業団地開発の現状と、その先に描く街づくりのビジョンについて、詳しくお話をうかがいました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。
東急不動産が描く次世代産業団地の未来
川村: 石井さん、今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。まず、御社が手掛けられている産業団地開発について、従来の物流倉庫開発とは異なるアプローチをされているとお聞きしました。その背景から教えていただけますか?
石井:ありがとうございます。我々東急不動産は、元々街づくりのDNAを持つ会社でして、渋谷でもたくさんの街づくりをさせていただいています。やはり「点から面」という形で事業を大きくしていく、そういったことに喜びを感じるメンバーが多いということもありますし、デベロッパーとして、そこに住まわれている方や事業者様といろいろなお話をしながら一緒にものをつくっていく、そこに対する想いが強い会社だと思います。
物流倉庫についても、単体での差別化はなかなか難しいということを認識しておりますので、これからは物流倉庫をはじめ、データセンターや農業といった様々な産業を組み合わせた街づくりを行い、それが結果的に地域の皆様に愛されて、我々としてもビジネスを拡大していければと考えています。
佐賀県鳥栖市「サザン鳥栖クロスパーク」:九州の交通要衝で描く未来図
川村: 具体的な事例として、佐賀県鳥栖市でのプロジェクトが注目されているとお聞きしました。どのようなプロジェクトなのでしょうか?
石井:「サザン鳥栖クロスパーク」と申しまして、2023年から24年にかけて、鳥栖市様が主催された産業団地開発事業者のコンペがありました。当社が代表企業となりまして、日本国土開発様や丸紅様といった企業様とコンソーシアムを組んで、我々が当選させていただいたプロジェクトになります(2025年4月に九州旅客鉄道様がコンソーシアムに参画され現在は4社で推進中)。
基本的な事業の考え方としましては、我々が農地を造成させていただいて整備を行い、そこに工場や企業の研究施設等を出店いただく企業様に向けて土地を分譲することを考えております。さらにその一角には、我々としても物流施設をはじめとした産業施設を出店していくということで、一体となった街づくりをしていくということを計画しております。
川村: 鳥栖市という立地を選ばれた理由は何でしょうか?
石井:鳥栖市は、九州の縦横に伸びる高速道路の結節点、交通の要所ということでありますし、小郡鳥栖南スマートインターチェンジに近接しておりますので、将来、高速道路といった幹線輸送で自動運転が実現された時には、そのメリットを享受できる希少な立地として我々は着目しています。
また、2021年以降に約50件の新規の出店企業様が九州に工場等を出店しているということもありまして、非常に注目しているエリアであります。
川村: 自動運転の話が出ましたが、高速道路を降りた後の「ラストワンマイル」についてはいかがでしょうか?
石井:自動運転は、まずは高速の区間から始まると思いますけれども、そこから先についても工夫を凝らすことで、ほぼ自動運転と変わらないような形で皆様には使っていただけるのではないかと思っています。
川村: やはり、ドライバー不足の話もそうですし、東から西、北から南へ、一人のドライバーさんが全部走るという建付けではない法律に変わってきているので、自動化の話は進んでいきますよね。
GX・DX・BCP統合戦略:企業単独では困難な技術を街レベルで実現
川村: 今回の開発では、GXやDXといった取り組みも重視されているとお聞きしました。具体的にはどのような内容でしょうか?
石井:我々東急不動産という会社は、再生可能エネルギーに非常に力を入れている会社でございまして、この街づくりにおいても、物流倉庫においても、そういった再生可能エネルギーといったものをしっかりと打ち出していきたいと思っております。
物流倉庫であれば、屋根の上に太陽光パネルを設置して、その自家消費で電力をすべて賄えるようにしたり、あるいはそれを街全体に広げていって、街が再生可能エネルギー100%で運用できるような産業の街づくりを目指していきたいと思っています。
DXの方で申しますと、例えば街全体で次世代の高速の通信インフラを引き込んだり、あるいは街の中で自動運転車両を走行させたり、DXでも様々な取り組みが、これから実現可能になってくると思っております。
川村: それらの技術導入において、コスト面でのメリットはあるのでしょうか?
石井:DXとGXそれぞれに共通する考え方としては、ご出店いただく企業ではなかなか導入が難しいような技術であっても、我々が街全体に供給することで、それを皆さんに享受していただける、そこに我々の街づくりの意義があるのかなと思っています。
新しい技術を取り入れましょうと言った時に、もう分かりやすく言ってしまうとお金はいくらでもかかるわけじゃないですか。それをやはり参画されている皆さんでシェアをすることで享受し合える関係ということです。
川村: BCPの観点からはいかがでしょうか?
石井:今回開発する産業の街づくりは、敷地の中に公園を作ったり、地域の皆様が集まる拠点、コミュニティスペースをご用意するという計画です。その中で有事の際には数日間の滞在が可能となる避難場所になる等のインフラの提供が可能となりますので、地域の防災を支えていければなと思っています。
埼玉県白岡市:物流と農業の融合で実現する6次産業化
川村: もう一つの注目事例として、埼玉県白岡市でのプロジェクトについてもお聞かせください。こちらでは農業との連携もされているとか?
石井:はい。埼玉県の白岡市というところで約27ヘクタール、元々耕作放棄地であった土地があるのですが、ここを宅地に転換して、その一部で2棟合計約4万坪ほどの物流倉庫を建てています。それ以外の土地については他の事業者さんと組ませていただきながら、その農地を再生するということをやっております。
川村: どのような農業を展開されているのでしょうか?
石井:場所によって様々あるのですが、例えばハウス栽培で、イチゴを高効率で作ってみたり、あるいはイチゴ狩りに訪れて体験していただけるような施設もあります。それから、生産、加工、流通、販売までを一貫して行う6次産業化施設といったものも我々で手掛けていきたいと思っておりますので、まさに物流倉庫と農業を掛け合わせた産業の街づくりという新たな形で展開していければなと思っています。
川村: イチゴ栽培で何か革新的な取り組みはありますか?
石井:一番北側にあるエリアでは、天井が5メートルぐらいあるビニールハウスを作っているのですが、そこではイチゴを段々形式で栽培しています。
普通の路地のイチゴって、畝を作ってそこで栽培しますよね。あれって結局この畝の部分でしかイチゴを作れないじゃないですか。通路部分は空けておかなければいけない。でも段々にするとぎっしりとイチゴを栽培できるんですよ。
これを、我々だけじゃなくて、サラダボウルさんという農業法人さんと組ませていただいて一緒に行っているんです。
組織体制:川上から川下まで統括する戦略的推進体制
川村: このような複合的な開発を進める上で、社内の体制はどのようになっているのでしょうか?
石井:私が所属する部署は、この産業団地全般のしっかりとした戦略を立てて、それを推進する役目です。この産業団地は、土地を用意するメンバー、それからその産業団地の中の企画、先ほどのGX・DXのような企画をするメンバー、それから実際に企業誘致をするメンバーということで非常に多くのメンバーが関わっているのですが、私がその舵取り役として戦略を立てて、どういった街づくりをしていきたいかというようなビジョンを打ち出し、メンバーを牽引しています。基本的には私のところで川上から川下まで全てを見ていくという役割です。
労働力確保:地域と共生する立地戦略
川村: 物流施設の運営において、労働力の確保は重要な課題だと思います。その点はいかがでしょうか?
石井:鳥栖市は、先ほど交通の要所という話もしましたけれども、近くを見ていただくと非常に人口の集積もありますし、少し行ったところには大型のショッピングセンター、ショッピングモールなんかもございます。元々人口については厚い地域でもあるのですが、さらに我々がこういった産業の街づくりをすることで、多くの人にお住まいいただいて、関係人口が増えていくということを実現していきたいと思っています。
埼玉県の白岡につきましても都心からも至近ですし、車でのアクセス、それから電車のアクセスも優れておりますので、そこは非常に自信を持っているところです。
川村:今までだと、用地が安く取得できるところ、イコールあまり人が住んでいないところに倉庫拠点があったりして、その中で働く人にとっては通勤が難しいというケースが結構ありましたよね。
それで言うと、地域全体の観点から考えられたからこそ、働きやすい立地や拠点の作りになっているんじゃないかと思います。
産学官民連携:実証実験の場としての産業団地
川村: 今回の開発では、様々なステークホルダーとの連携も重視されているとお聞きしました。
石井:この産業団地は、産学官民が連携して開発されています。産が事業者、官は佐賀県や鳥栖市、学は大学や研究機関、それから民は地元の方々です。こういった皆さんと連携をしながら産業の街づくりをしていきたいと思っておりまして、一つ具体例を上げますと、非常に広大な街づくりですので、様々な実証実験ができると思っております。
なので、私どもが手掛ける物流倉庫、それからその他の産業不動産を、出店企業様と連携しながら、最新技術の実証実験の場といったような形で、街づくりを進めていければなと思っています。
ブランド戦略:「GREEN CROSS PARK」で描く全国展開
川村: 最後に、これらの取り組みを統括するブランド戦略についてお聞かせください。
石井:東急不動産は、鳥栖や白岡のような産業を絡めた街づくりを広く展開していきたいと思っておりまして、それらの考え方を基にしたブランディングの名前がグリーンクロスパークです。
川村: 「サザン鳥栖クロスパーク」という名前の由来も教えていただけますか?
石井:。サザンは鳥栖市の南側にあるという意味、クロスは場所を表し、縦横の高速の結節点という点からです。非常に覚えやすい名前だと思います(笑)。
物流業界への示唆
川村: 本日お話を伺って、単なる物流倉庫開発ではなく、まさに街づくりの開発だと感じました。
石井:そうですね。我々も物流倉庫をたくさん全国で作らせていただいておりますけれども、やはりおっしゃるように、なかなか単体での差別化は難しいと認識しております。だからこそ、これからは物流倉庫やデータセンター、それから農業といったような様々な産業を組み合わせた街づくりを行い、それが結果的に地域の皆様に愛されて、我々としてもビジネスを拡大していければなと思っています。
従来の物流施設開発から脱却し、GX・DX・BCP機能を統合した「産業の街づくり」で差別化を図る東急不動産の取り組み。単体施設では実現困難な付加価値を街レベルで創出することで、テナント企業、地域住民、そして開発事業者の三方良しを実現する新しいモデルとして、今後の展開が注目されます。
企業プロフィール
会社名:東急不動産株式会社 (英語名 TOKYU LAND CORPORATION)
本社所在地:東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ
設立:1953年12月