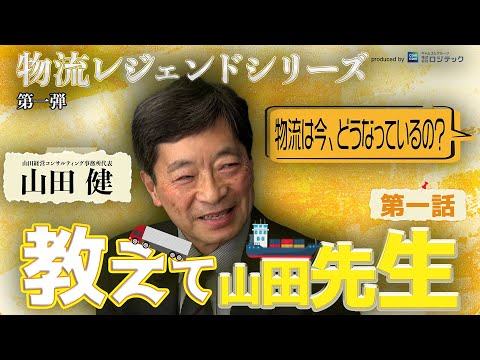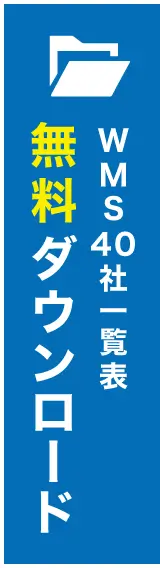目次
倉庫や物流センターで働いていると、荷物が棚やパレットから少し飛び出しているのを見かけることがあります。この状態を指すときに使われるのが「オーバーハング」という言葉です。
専門用語ではありますが、現場の安全や効率に直結するため、輸送や保管に関わる人なら必ず知っておきたいポイントです。
「ちょっとくらいはみ出していても問題ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし実際には、作業事故や荷物の破損、さらには全体の作業効率にまで影響する場合もあります。
この記事では、オーバーハングの基本的な意味や原因、現場でのリスク、さらに防止策までを詳しく解説します。
- オーバーハングとは、荷物が棚やパレットからはみ出した状態のこと
- 安全面・品質面・効率面で大きなリスクを引き起こす要因になる
- 近年はICTやマテハン技術を活用し、防止の取り組みが進んでいる
オーバーハングとは?
倉庫や工場で荷物を棚やパレットに保管したとき、本来のサイズを超えて外に突き出してしまうことがあります。この状態が「オーバーハング」と呼ばれています。
例えば、パレットのサイズが1100mm×1100mmなのに、1200mm幅の段ボールを積んでしまうと、必ずどちらかがはみ出すことに。見た目にはわずかな差でも、実際にはその部分に支えがないため、荷物は不安定な状態です。
高さのあるラックに収納した場合、突き出した部分が下の通路にせり出すような形になることもあり、作業者がフォークリフトや台車で通過するときに接触するリスクも考えられます。
なぜオーバーハングが起きるのか

なぜオーバーハングが発生するのでしょうか?ここでは、どんな場合にオーバーハングが発生するかを解説します。
荷物サイズと棚・パレットの不一致
物流現場では、必ずしもすべての荷物が規格通りに梱包されているわけではありません。
出荷元によって箱の大きさが異なり、パレットのサイズに収まりきらない場合があります。
荷姿のばらつき
同じ商品でも製造ロットや輸送条件によって梱包が変わることがあります。
段ボールの強度や形状が違えば、積み付け時にきれいに収まらず、結果的にはみ出してしまうのです。
作業上のミスや経験不足
新人や応援要員が作業するときに、正しい積載位置を知らずにずらして置いてしまうこともあります。特に繁忙期で作業が急がれているときには、つい位置合わせが雑になり、オーバーハングが発生しやすくなります。
コスト優先の梱包
製造メーカーによっては「1箱でも多く製品を詰めたい」という理由から、段ボールを大きめに設計している場合があります。
結果としてパレットに合わず、はみ出しが発生する原因になります。
オーバーハングがもたらすリスク
物流現場でオーバーハングが発生することにより、様々なリスクの発生が考えられます。
ここでは想定される4つのリスクについて解説します。
落下事故の可能性
突き出した荷物は安定感がなく、わずかな振動や衝撃で落ちてしまうことがあります。
特にフォークリフトで高所に上げたとき、オーバーハング部分がぐらつきやすく、下で作業している人に落下すれば大事故になりかねません。
荷物の破損・品質低下
支えのない部分は重さに耐えられず、箱が潰れたり、内部の商品が変形したりすることがあります。
食品や精密機器では品質クレームに直結し、メーカーにとって大きな損失となります。
作業効率の低下
フォークリフトの爪をパレットに差し込む際、はみ出し部分が邪魔になり、うまく入らないことがあります。その結果、荷物をまっすぐ持ち上げられず、予定通りの位置に戻せないケースもあります。
こうした状態が続くと、システムで想定した配置通りに保管できなくなり、出庫や棚替えの作業効率が下がる要因になります。
保管スペースの有効活用を妨げる
はみ出した荷物は隣のスペースに干渉し、ラックの有効活用を妨げます。
結果として本来ならもっと収納できるはずのスペースが無駄になってしまいます。
物流現場でのオーバーハングに関する対策

倉庫での保管貨物はさまざまな種類があるため、オーバーハングはどの現場でも発生する可能性があります。そのため、物流現場ではオーバーハングに関する対策が欠かせません。
ここでは3つの対応策の例について解説します。
標準パレット・ラックの利用
標準パレットやラックを使うことで荷物が安定し、オーバーハング防止に効果があります。
国際物流ではISO規格、日本国内ではJIS規格が主流ですが、欧州規格なども混在しているのが現状です。
そのため、統一を進めつつ、載せ替えサービスやラック調整など柔軟な対応も求められています。
荷姿改善の依頼
サプライヤーやメーカーに対し、段ボールのサイズや強度を見直してもらうことも有効です。
たとえば「パレットサイズに収まる箱寸法にしてほしい」と依頼する取り組みは、共同配送を行う企業でも進んでいます。
作業教育とルール化
新人教育の中で「荷物はパレットの角を合わせて置く」などの基本ルールを徹底することが大切です。さらに、定期的に現場点検を行い、オーバーハングがあれば指摘する仕組みを作ることで習慣化できます。
ICT・マテハン技術による防止
近年の物流業界では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展とともに、オーバーハング防止の取り組みも進化しています。
AIカメラの導入
- 棚やラックに保管された荷物を常時監視
- はみ出しを検知するとアラートを出す仕組み
- 人の目に頼らず、即座に異常を発見できる
自動積付けロボット
- EC物流や共同配送など多品種・大量出荷の現場で活用
- ロボットが最適な配置で荷物を積む
- 人為的なオーバーハングをほぼなくせる
WMS(倉庫管理システム)との連携
- 荷物の寸法情報を事前に登録
- システムが適切な保管場所を指示
- 勘に頼らず、データに基づく配置でリスクを抑制
まとめ
オーバーハングは単なる「荷物のはみ出し」ではなく、現場の安全や品質、作業効率に直結する重要な課題です。
原因は荷物サイズの不一致や作業ミス、梱包設計の問題などさまざまですが、対策を講じることで大幅にリスクを減らせます。特に近年はAIやロボット、WMSなどの技術活用により、オーバーハングを未然に防ぐ仕組みが広がっています。
倉庫での日常業務の中で「荷物が正しく収まっているか」を意識することは、安全で効率的な現場づくりに欠かせない第一歩となるでしょう。
オーバーハングに関するよくある質問とその答え
Q1. オーバーハングは、少しのはみ出しであれば問題ないですよね?
A. たとえ数センチでも落下や破損のリスクはあります。
見過ごさず、必ず修正する習慣を持つことが大切です。
Q2. どのような現場でオーバーハングが多く見られますか?
A. EC物流や共同配送のように多種多様なサイズの荷物を扱う現場で多発します。
また、繁忙期や応援作業者が多い現場でも起きやすいです。
Q3. 新人ができる具体的な予防策はありますか?
A. 荷物を置くときは必ず「角を合わせる」ことを意識してください。
また、違和感を覚えたらそのままにせず、先輩や上司に確認する習慣をつけましょう。
小さな気づきが大きな事故を防ぎます。