
各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
車両不足が深刻化する物流業界で、古くからある「求貨求車」という荷物と車のマッチング手法が再び注目されています。多くのIT企業が参入し、DX投資も活発化する一方で、収益化に成功している企業は限定的という現実があります。 今回は、物流業界の専門家・山田経営コンサルティング事務所 代表の山田健さま(以下、敬称略)との対談企画第4弾。IT化を阻む構造的課題と、新たなビジネスチャンスについて、お話を伺いました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。
【山田さまとの対談シリーズその他の記事はこちら】
第1弾:物流現場取材シリーズ【22】変革の時、物流業界の未来を拓く羅針盤(山田経営コンサルティング事務所様)
第2弾:物流現場取材シリーズ【25】数字で変わる業界構造改革の実現ー物流コンサル山田氏
第3弾:物流現場取材シリーズ【26】物流コンサル山田氏流「失敗しないコンサル見極め術」
昔からあった効率化の知恵
川村: 今日は求貨求車(きゅうかきゅうしゃ)について詳しくお話を伺いたいと思います。最近はITを使ったマッチングサービスが話題になっていますが、そもそも求貨求車の歴史はどのようなものなのでしょうか。
山田: 実は求貨求車というのは、決して新しい仕組みではありません。ネットが普及するよりもずっと前から、運送業界では効率化のための知恵として使われてきました。昔は「水屋さん」という貨物利用運送業者がいて、荷物と車をつなぐ役割を担っていました。また、私たちの会社では「輸送調整所」という部署があって、地域ブロックごとに情報を集めて車の往復を効率化していたのです。
川村: 具体的にはどのような仕組みだったのですか。
山田: 例えば、関東から東北に行く便と、東北から関東に来る便が別々に動いていることがあります。それを調整して、同じ車で往復させることで、空車(からしゃ)での移動を減らしていました。長距離輸送では「帰りが空じゃもったいない」というのは、誰でも考える自然な発想ですから。
川村: なるほど。でも一般的には、トラックの多くが空車で走っているというイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。
山田: それについて興味深い事例があります。ある製紙メーカーさんから「うちの物流子会社の帰り便が空だから調べてほしい」というコンサル依頼を受けたことがありました。中部地区から関東に製品を運んで、帰りは空で戻っているはずだと考えられていたのです。
川村: 結果はいかがでしたか。
山田: 調べてみると、なんと9割以上が往復で荷物を運んでいました。帰りには関東から中部に向けて紙の加工品などの荷物があったのです。ところが、その結果を報告したらお客さんに非常にがっかりされました。おそらく「今は帰りが空車になっているから、帰りも荷物を運ぶようにして運賃を下げよう」という意図があったのでしょう。
なぜロジリンクジャパンは失敗したのか
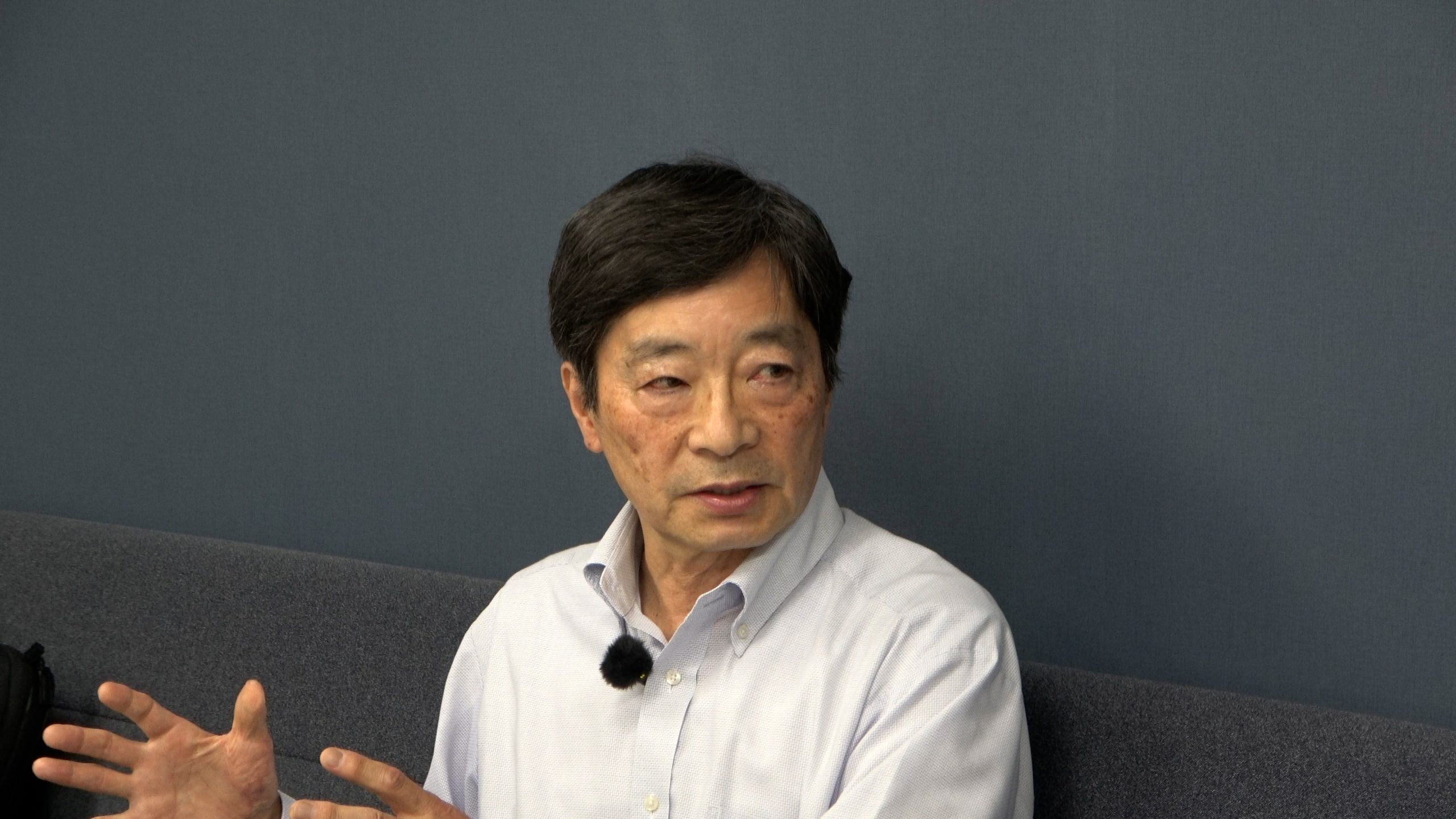
川村: 現在はITを活用した求貨求車システムがたくさん登場していますが、過去にも大きなプロジェクトがあったと聞いています。
山田: そうですね。2000年頃に「ロジリンクジャパン」というプロジェクトがありました。国の関連省庁がバックアップし、大手商社や大手物流会社が出資してITマッチングの会社をつくったのです。当時としては革新的な取り組みでした。
川村: それはすごいですね。結果はどうなったのでしょうか。
山田: 残念ながら4年で解散してしまいました。最大の問題は、参加する企業が少なかったことです。
川村: なぜ参加企業が少なかったのでしょうか。皆さん同じような課題を抱えているはずなのに。
山田: 出資者が大手企業だったため、参加のハードルを高く設定しすぎたのでしょう。参加資格や費用負担などの敷居が高くて、本当に困っている中小の運送会社は参加できませんでした。しかし実際に荷物を運んでいるのは、そうした中小事業者がほとんどなのです。大手が保有するトラックの台数なんて、全体から見ればごく一部ですから。
川村: 現在も多くのIT企業がマッチングサービスを展開していますが、状況はいかがですか。
山田: ITは単純なマッチングサービスというのは得意だと思いますが、物流業界はそれだけではうまくいかないと思いますね。個別ルールがたくさんあるので(苦笑)。
手書きメモが消えない理由
川村: ITでのマッチングが思うように進まない理由について、もう少し詳しく教えてください。
山田: 最大の問題は、運送業務が標準化されていないことです。単にAからBに荷物を運ぶだけではなく、「納品先のこの受付に行って、伝票をこうやって渡して、帰りに何かを引き取ってこい」といった細かい指示が必ずついてきます。
川村: そうした情報をシステムに入力するのは難しいということですね。
山田: そうです。実際に運送会社の配車表を見ると、Excelで作ってあるのですが、手書きでびっしりと書き込みがしてあります。それをデジタル化しようとしても、手書き部分が多すぎてとても対応しきれません。
なぜ宅配便マッチングは機能するのか
川村: 一方で、比較的うまくいっているマッチングもあるのでしょうか。
山田: ネット通販の配送分野では、マッチングが比較的機能しています。これは非常に標準化が進んでいるからです。伝票も配達方法も標準化されていて、日々の単発作業として個人の配送事業者でも対応しやすい環境が整っています。
川村: 事業者が標準を決められるから、イレギュラーが起きにくいということですね。
山田: そうです。宅配便という業務自体が、この業界の中では最も標準化が進んでいる分野なのです。伝票も届け方も決まっている。だからマッチングサービスも機能するわけです。
川村: 少し似た業界で、タクシーだと最近はアプリによる配車が進んでいますよね。
山田: タクシーの場合は、乗るお客さんの人数や荷物の大きさなど、ある程度の幅はあっても基本的には「人を運ぶ」という標準化された作業です。しかし貨物の場合は、荷物の種類、大きさ、重量、取り扱い方法など、すべてカスタマイズが必要になります。これがマッチングを複雑にしている要因の一つです。
これからの求貨求車に必要なことは?

川村: 求貨求車をビジネスモデルとして上手に成立させるには、どのようなことが必要だと思われますか。
山田: 難しいところですね。物流業界は、人が対応しないといけない部分と、比較的標準化された部分があるので、狙うとしたらやはり標準化された部分だと思います。あとは、現在、求貨求車事業は市場が飽和状態です。ですから、プラスアルファのサービスを提供して、そっちで利益を得るような仕組みにするというのも一つではないでしょうか。
川村: 求貨求車事業は、飽和が近づいているから利益が出ないということでしょうか。
山田: こういうのは、集約の効果が大きいですからね。情報が多い方が有利なので、今から同じ市場に、同じ条件で進出するのはハードルが高い気がします。もしこれから進出するなら、今はまだ多くの人が気付いていないニーズを探すことが必要ですね。物流マーケットは広いので、ニッチな分野を探しつつ付加価値を与えることができれば勝算があります。
川村: なるほど。貴重なお話をありがとうございました。
山田: こちらこそ、ありがとうございました。
山田さまとの求貨求車に関する対談は、以下のURLから動画でもご覧いただけます!
【物流レジェンドシリーズ】山田先生に聞く!求荷求車システムとどう向き合う?
https://youtu.be/bkS6duik47s?si=MA-TlGpB2CReyxWI
企業プロフィール
会社名:山田経営コンサルティング事務所
本社所在地:東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
設立:2014年6月








