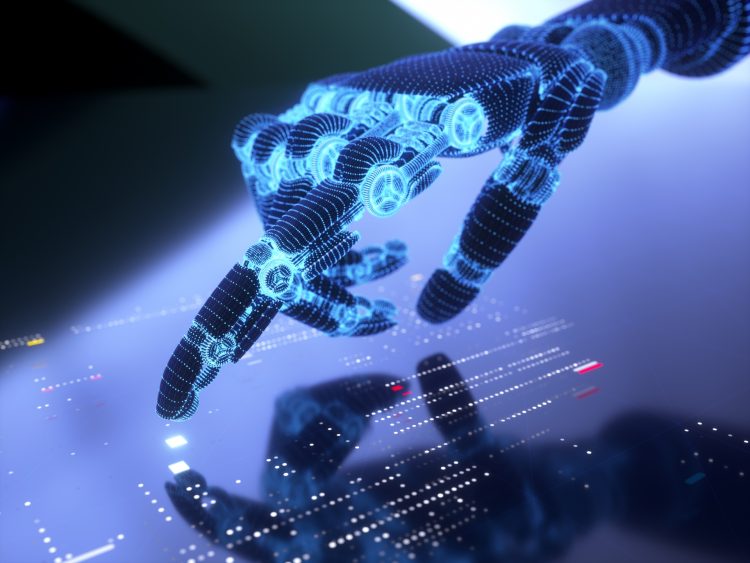各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
物流2024問題による業界再編が進む中、DXブームに沸くマッチング市場は本当に持続可能なのか? 今回は、運送業界の構造変化と物流テック市場の未来について、業界に精通するコンサルタント・山田経営コンサルティング事務所 代表の山田健さま(以下、敬称略)との対談企画第5弾。物流DXの現実と今後3~5年で予想される市場再編の行方を伺いました。モデレーターを務めるのは、株式会社ロジテック代表取締役の川村です。
【山田さまとの対談シリーズその他の記事はこちら】
第1弾:物流現場取材シリーズ【22】変革の時、物流業界の未来を拓く羅針盤(山田経営コンサルティング事務所様)
第2弾:物流現場取材シリーズ【25】数字で変わる業界構造改革の実現ー物流コンサル山田氏
第3弾:物流現場取材シリーズ【26】物流コンサル山田氏流「失敗しないコンサル見極め術」
第4弾:物流現場取材シリーズ【28】求貨求車DX収益化の壁と突破戦略ーー物流コンサル山田氏
業界別に見る物流DXの成功パターン
川村: 物流DXが成功しているのは、どういう分野でしょうか。何か事例があれば教えてください。
山田: 例えば、医薬品卸業者をコンサルしたことがあるんです。あれって結構、社員がルート配送的に街のドラッグストアに行く場合もあるんです。配送しながらセールスしているという名目ですが、実際はセールスしていないんです。ただ届けているだけで、むしろそこは、もっと分業化した方がいいところがたくさんあります。
川村: それは面白い発見ですね。つまり、営業と物流を分けた方が効率的だということですか。
山田: そうなんです。言い方は悪いですが、営業をあまり回らない言い訳に配送を使っている感じがするんです。「これを配送しなければいけないから」という、逃げになってしまっている部分があります。そこは皆さん気づいてきていて、その分業を今後進めなければいけないねという話にはなってきています。
川村: 医薬品以外にはどんな業界で可能性がありますか。
山田: 食品業界もそうです。大手じゃなくて、中小の食品業者でそういうことがあるんですね。例えばドライアイスを配送するとか、冷凍食品をお店に配送するとか、そういうところに向けて専用の配送をやる人というのは結構必要になってくると思います。
川村: なるほど。ニッチな分野ほど、まだ効率化の余地があるということですね。
山田: まさにそうです。やはり物流って、その周辺まで見ると大きなマーケットだと思います。
バース予約システムにみるDX導入の光と影

川村: 物流DXの代表例として、バース予約システム(※1)がありますよね。これについてはいかがでしょうか。
山田: それこそ当たり前のようで、今まで誰もやっていなかったんです。だって我々がお医者さんに行く時、歯医者さんに行く時、みんなネットで時間予約するじゃないですか。この業界はやっていなかったんですからね。「朝10時必着」とか「午前中必着」っていう、こういうアバウトな指定しか今までなかったわけです。
川村: でも実際に導入してみると、課題もあるのではないでしょうか。
山田: そうなんです。バースシステムを入れると倉庫側はいいんです。何時から何時までにどういうトラックが何台来るか、全部わかるから、それに合わせて作業ができます。けれど運送会社側からすると、例えば1日何カ所も配送していく時に、「Aの場所に10時に行ったらBの場所は11時に行きたい」んですよ。ところが、そのとおりに予約が取れないなんてことがしょっちゅうあるわけです。今まではアバウトだったから自分のペースで回っていけたのに、配送ルートの順番が自分の都合で組めなくなるんですね。
川村: 確かに、トラック側からすると不便ですね。
山田: そういう場合は電話をして、もうシステムじゃどうしようもないので「なんとか11時に取ってよ」みたいな、こういう交渉を結構やっています。その交渉でかえって忙しくなったという話を聞きました。
物流の場合、サプライチェーン(※2)全体にまたがってしまうので、どこかを最適化するとその歪みがどこかに来る、こういう問題がついてまわります。だから難しいんです。
川村: それは皮肉な話ですね。DXで効率化したはずなのに、かえって手間が増えてしまったんですね。
山田: だからダメということではないんですよ。絶対あった方がいいとは思うんですが、サプライチェーン全体をコントロールできるプレイヤーというかリーダーみたいなのが必要です。
川村: 課題の根本解決ということですね。
山田:でもそれは同一業界の中だけでいいと思うんです。例えば食品業界なら食品業界だけで最適な仕組みを作ると、結局物流というのは業界の中で動いていますから。そういう中で、いわゆるプラットフォーム的なものができて、そこに情報が全部集まって、同じルールで物が流れるみたいな仕組みができるといいなといつも思っているんです。
※1 バース予約システム:トラックが倉庫で荷物を積み下ろしする場所(バース)の利用時間を事前にネット予約できるシステム
※2 サプライチェーン:原材料の調達から製造、販売、物流まで、商品が消費者に届くまでの一連の流れ
成功している中堅運送会社の共通項と業界改善の流れ
川村: 中堅どころの運送会社さんなんかは、とてもフレキシブルで新しいことに取り組むところが多いですよね。
山田: そうですね、そういうところは社長が物流を知っていますから。だってみんな自分でトラックを運転していた人だから。やることがすごく的確で、利益率がめちゃくちゃ高いでしょ。
川村: なるほど、現場出身の経営者の強みということですね。
山田: そうです。例えば丸和運輸さんがAmazonのデリバリープロバイダー(※3)を始めた時に、我々は「えっ!」と驚きました。大手が大赤字を出している宅配をよく受けるなと思ったんだけれど、しっかり利益を出したんです。さすがだなと思いました。
川村: それって、DX化にも似たようなことが言えるかもしれませんね。ITの仕組みとしては素晴らしくても、業界をわかっていないとうまくいかないという。
山田: それは大きいです。ただ、このバランスは難しくて、業界をわかりすぎちゃってると新しい発想はできなくなります。だから新しい技術や発想を取り入れつつ、実際の現場のこともわかっているというバランスがうまく取れていると強いんじゃないでしょうか。
川村: バランスという話がでましたが、今回の法改正によって、制限されるべきところが制限されるようになったことで、ソリューションが生まれやすくなった側面もあるのでしょうか。
山田: それは確かにフォーカスされてきますし、そこに取り組まざるを得なくなってきています。特に今回の法改正を見ていると、結構報告をしなければいけないですよね。ちゃんと「これやりました」「目標こうです」と、1年ごとかな。あれをやるには、本気の対応が必要になる気がします。
川村: 別の業界からしたら当然のことかもしれませんが、物流業界にとっては大きな変化ですね。
山田: そうです。今までのように「こうしなさい」ということを言っているだけじゃ誰もやらなかったわけです。それが今は義務化されて、チェックもされるようになったっていうのは大きな進歩じゃないですか。
※3 デリバリープロバイダー:Amazonが直接契約する配送業者
3~5年後の物流マッチング市場予測
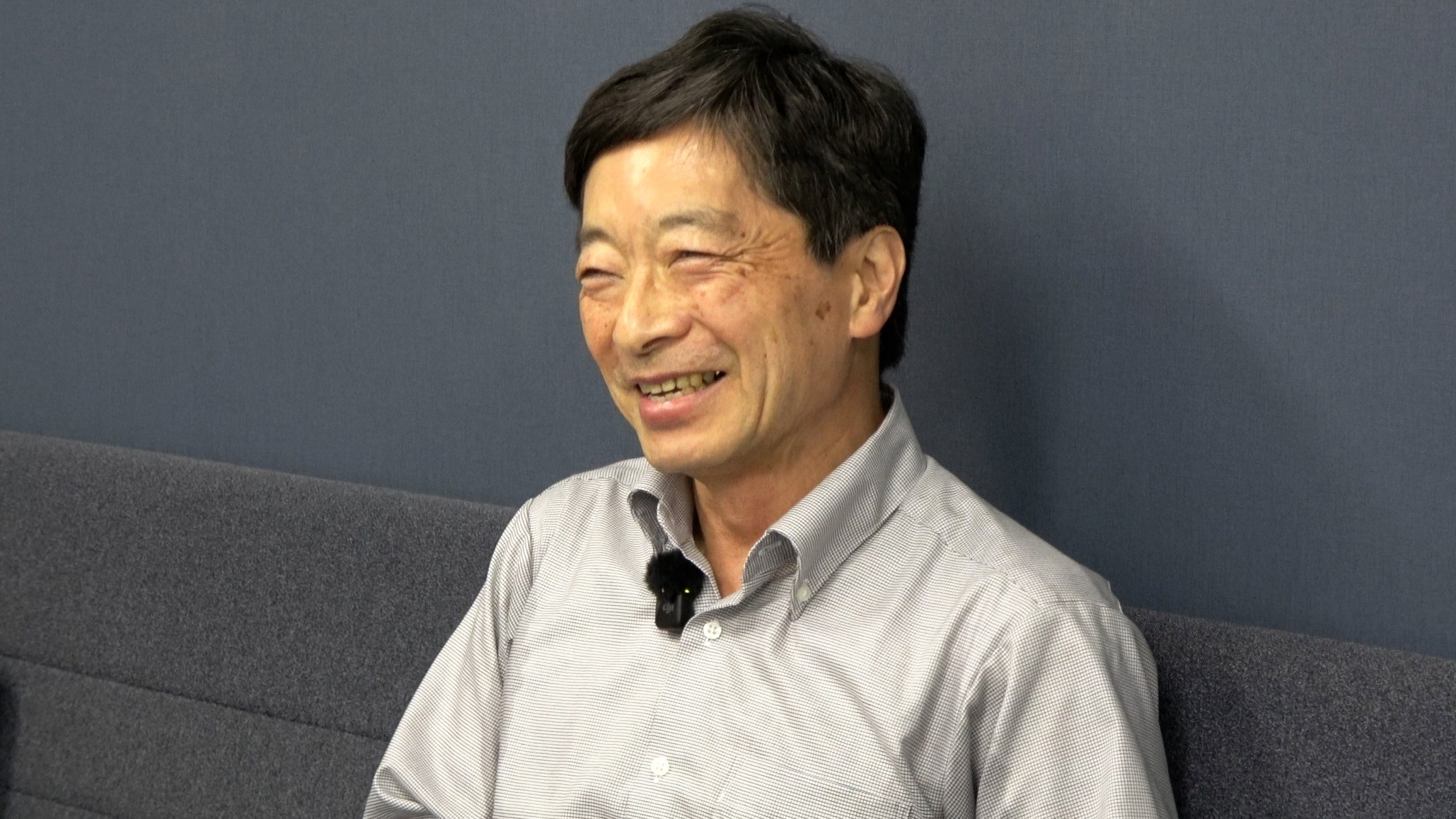
川村: では、3年、5年経った時に、この市場やマッチングのモデルはどういう形になっていると予想されますか。
山田: 今、こういうマッチングが成り立っているっていうのは一つ、物流事業者の数が多いっていうのがあります。かつて3万8000社だったのが6万社になったという。競争が激化しているっていうのがあるからこそ、こういうマッチングが成り立つんじゃないでしょうか。
川村: でも、それが変わってくるということですね。
山田: 間違いなく事業者数は減ってくるし、ドライバー自体も減ってきます。さらに考えられるのは、ある程度大手に集約されていく動きは、どうしても出てこざるを得ないような気がします。それなりにドライバーの待遇を上げていこう、教育もきちんとしていこうとすれば、それなりの規模の企業は必要じゃないですか。
川村: そうですね。
山田: あと、運賃交渉力は、やはり規模に比例します。そうやってある程度集約化され、規模も大きくなってきた時に、今と同じくらいマッチングの必要があるかなっていうのはちょっと疑問に思います。
川村: マッチングモデルは、小規模な事業者だとか個人だとか、そういうところのマッチングが多いので、運送会社が大手に集約されていくと、そこの形は大きく変わるということですね。
山田: そうならざるを得ないんじゃないかなと思います。ただし、B2Cはまた別です。これは別として、従来のB2Bの市場っていうのは、そっちの方向に行かざるを得なくなってくるように思うんです。物流2024問題とかまた法律で規制が入ってくると、それに対応する業者への統合って当然進みますから。その時に今と同じマッチングの機能が必要なのかどうかという気がします。
川村:B2Cは、軽貨物だとか個人プレイヤーの参入が、しやすいという意味で言えば、法律が大きく変わったりすればまた別の話かもしれませんね。
山田: そうですね。あと働き方の問題もあります。個人で組織に縛られずに働きたいという人が、今後増えるのか減るのか、ちょっとそこが今一つ読めません。
川村: ではB2Cの領域であれば、マッチングサービスのモデルも売れる可能性はありますか?
山田: どうですかね?売れたとしても、利益が出ますかね(笑)?
川村: さっきの話で、荷主さんと運送会社さんの困りごとを、マッチングだけじゃなくて周辺のサービスと掛け合わせていくとどうですか。
山田: やるとしたらそうですね、マッチングは一つの手段として、その周辺需要とかそこに新しいニーズとかいうものを開発して、そっちで利益を出すってのは十分ありだと思います。
川村: たくさんのヒントをいただきました。今後の事業運営の参考にさせていただきます。山田さん、貴重なお時間をありがとうございました。
山田: こちらこそ、ありがとうございました。
山田さまとの求貨求車に関する対談は、以下のURLから動画でもご覧いただけます!
【物流レジェンドシリーズ】山田先生に聞く!求荷求車システムとどう向き合う?
https://youtu.be/bkS6duik47s?si=MA-TlGpB2CReyxWI
企業プロフィール
会社名:山田経営コンサルティング事務所
本社所在地:東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
設立:2014年6月