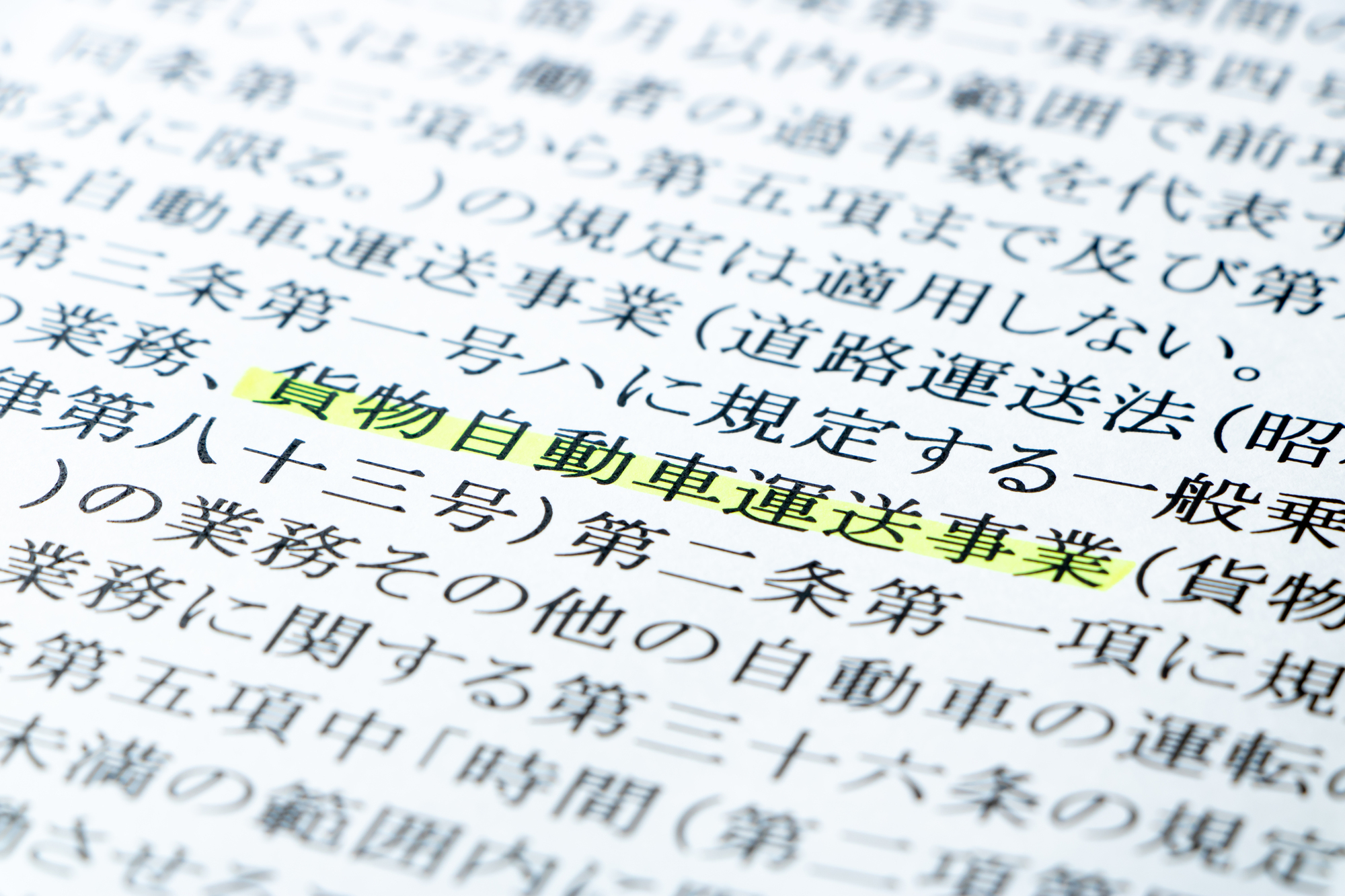
目次
- 許可は終身から5年更新制へ。違反・安全体制・財務次第で更新不許可=実質免許剥奪のリスク。
- 無許可運送(白トラ)への委託は禁止を明確化。許可確認を怠った荷主にも責任が及ぶ。
- 実運送体制管理簿の作成・1年保存を義務化。真荷主の閲覧・謄写で委託階層が見える化。
2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法では、物流業界に大きな制度変更がありました。
主なポイントは、許可の5年更新制の導入、無許可運送(いわゆる白トラ)への委託禁止の明確化、そして実運送体制管理簿の作成義務化です。
いずれも現場に直接影響する内容であり、今後は「違反の放置」が企業存続に関わる可能性も出てきました。
終身許可から5年更新へ
これまで運送事業の許可は、取得すれば半永久的に有効とされてきました。
しかし改正後は、5年ごとに更新審査を受ける仕組みに変わります。
審査では、法令順守・安全管理・財務の健全性などが確認され、違反の多い事業者や改善が不十分な場合は、更新が認められない(=実質的な免許剥奪)可能性もあります。
たとえば、過積載や長時間労働などの違反を放置していた場合、数年後の更新審査で評価を下げる要因になりかねません。
小さな違反も「後で効く」――。この時間差リスクこそ、今回の改正で最も注意すべき点です。
「白トラ」委託は荷主も責任に
これまで曖昧だった無許可業者への委託(白トラ行為)について、改正法では明確に禁止が打ち出されました。
これにより、無許可業者と知りながら依頼した場合だけでなく、許可の有無を確認せず委託した場合も、荷主が責任を問われる可能性があります。
つまり「知らなかった」では済まされなくなったということです。
荷主は、委託先の事業許可証の確認や、契約書での再委託の制限明記を行うことが必須になります。
特に利用運送を介するケースでは、実際にどの会社が運んでいるのかを把握しておくことが重要です。
今後は、荷主側にも「適法な取引を行う責任」が問われる時代に変わっていきます。
実運送体制管理簿で“委託構造”が見える時代へ
新たに義務化された実運送体制管理簿は、運送の委託関係を可視化する仕組みです。
作成の対象となるのは、元請(利用運送事業者を含む)で、1.5トン以上の貨物を扱い、再委託を行うケースです。
自社で完結する運送であれば不要ですが、下請を使う場合は運送ごとに管理簿を作成し、1年間保存する義務があります。
また、真荷主(元請に発注した企業)には、閲覧・謄写を請求する権利が与えられています。
つまり、元請・下請・実運送者の関係が「見える化」され、違法な再委託や名義貸しがチェックしやすくなるということです。
依頼日/貨物概要/発注先名
下請名/契約日/輸送区間
車両番号/積込・卸日時
氏名/運送完了時刻/備考
保存期間:運送完了後1年間/真荷主は業務時間内に閲覧・謄写請求が可能です。
※様式は任意ですが、管理簿には「実運送事業者名」「貨物内容・区間」「請負階層」の3点を必ず記載してください。本図は、記載項目の流れを示すイメージです。
真荷主(発注者)
元請(利用運送)
下請(運送事業者)
実運送事業者(会社)
保存期間:運送完了後1年間/真荷主は業務時間内に閲覧・謄写請求が可能です。
※様式は任意ですが、管理簿には「実運送事業者名」「貨物内容・区間」「請負階層」の3点を必ず記載してください。これらが含まれていれば、配車表など既存帳票の転用でも要件を満たします。
制度強化の背景にある狙い
今回の改正は、ドライバーの長時間労働、低運賃、多重下請構造といった物流の慢性的な課題を是正する目的があります。
2024年問題で労働時間の上限規制が始まりましたが、それだけでは持続的な改善にはつながりません。
政府は「荷待ち・荷役時間の削減」「請負階層の抑制」「賃上げ原資の確保」を同時に進める方針を打ち出しており、今回の法改正はその一環といえます。
つまり、“働き方改革”の次のステージが、制度によるコンプライアンス改革なのです。
現場がすぐに取り組むべきこと
今回の法改正は、すべての物流事業者・荷主に関係します。
とりわけ次の3点は、今すぐに見直しを進める必要があります。
- 委託先の適法性を確認する
委託する際は、事業許可の有無や車両区分を必ず確認し、再委託条件を契約書で明確にしておきましょう。 - 管理簿の運用ルールを整える
管理簿をどの部署が作成・保存するのか、閲覧請求が来た際にどう対応するのかを社内で決めておくことが重要です。 - 価格だけでなく適法性で選ぶ
標準的運賃や適正原価の指針を参考に、原価割れの委託を避けましょう。安すぎる契約は、違反リスクと労務リスクの両方を高めます。
まとめ

改正後の制度は、単なる「ルール強化」ではなく、信頼できる企業を残すための再設計です。
違反を放置する企業は淘汰され、透明な運用を実践する企業が選ばれる時代へ。
許可の更新、委託契約、管理簿の整備――これらはすべて「取引の信頼」を守るための土台です。
荷主・運送事業者の双方が法令を正しく理解し、日常業務の中で“順守の仕組み”を作っていくことが、これからの物流経営に欠かせません。









