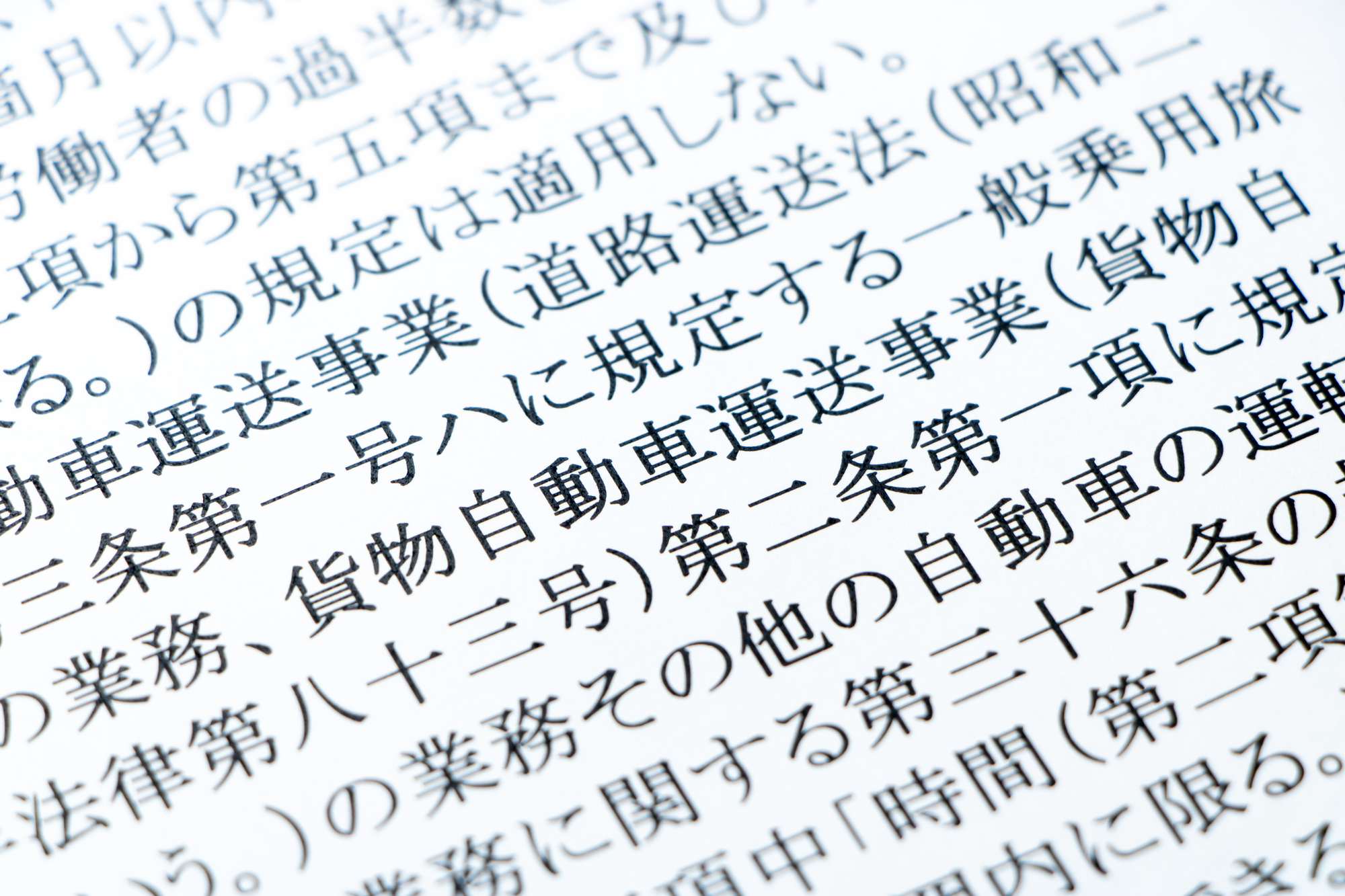
目次
2025年4月、運送業界において大きな制度改正が施行されました。
改正貨物自動車運送事業法です。
これにより、「実運送体制管理簿」の作成と1年間の保存義務が元請(利用運送事業者)に課されることになりました。
この改正の目的は、再委託構造の透明化と荷主への説明責任の強化。これまで不明確だった「誰が、どの区間を、どのような階層で運んでいるのか」を明確化し、荷主が運送実態を把握できるようにすることが新制度の狙いです。
帳簿整備を怠った場合、行政処分や許可更新時に不利な要因に。さらに、荷主から「運送体制が見えない会社」と判断されれば、取引継続にも影響しかねません。実運送体制管理簿への対応は、事業継続に関わる経営課題といえるでしょう。
一方で、この制度を適切に運用できれば、「透明性の高い信頼できるパートナー」として荷主から評価され、適正運賃交渉や新規取引獲得の武器になる可能性もあります。
本記事では、実務担当者が陥りがちな「落とし穴」を具体的に示しながら、現場で即実践できる対応策をお伝えします。
実運送体制管理簿とは何か

実運送体制管理簿とは、再委託を含む運送体制を記録し、運送実態を明らかにするための帳簿。対象となるのは、「1.5t以上の貨物を扱い、再委託を行う元請事業者」です。
【記載が義務づけられる3項目】
- 実運送事業者の名称
- 貨物の内容および輸送区間
- 請負階層(元請・一次下請・二次下請など)
この3点を案件ごとに整理し、1年間保存する必要があります。
また、真荷主(発注企業)は当該帳簿の閲覧・謄写を請求できます。
したがって、帳簿は「行政に見せるためのもの」ではなく、荷主との信頼関係を支える情報基盤と位置付けることが重要です。
対象ラインと実務上の「落とし穴」

義務の対象となる範囲については誤解が多く、「自社は対象外」と思い込むケースが見受けられます。しかし、次のような状況に該当する場合は、すべて管理簿の作成義務が発生するため、チェックしてください。
- 元請として受注した案件を他社に再委託している
- 繁忙期や臨時便で外部業者に輸送を依頼している
- 混載便で区間ごとに別業者が担当している
- スポット案件でも、再委託した時点で対象になる
また、軽貨物運送のみを扱う場合は対象外ですが、1.5t以上の貨物を扱う事業と併用しているケースでは、全体として管理簿作成義務が発生します。
現場で見落としがちな「5つの落とし穴」
落とし穴1:「うちは自社運行がメインだから大丈夫」という思い込み
自社車両比率が高くても、月に数件でも再委託があれば対象です。
年末年始の繁忙期対応や、突発的な増車依頼も見逃せません。
落とし穴2:口約束・LINEベースの再委託管理
「いつもの協力会社だから」と口頭やLINEで依頼しているケースは要注意。
記録が残らない運用では、帳簿作成時に遡及できず、虚偽記載のリスクがあります。
落とし穴3:配車担当者の属人化
ベテラン配車担当者の頭の中にしか再委託情報がない状態では、担当者の退職・異動時に帳簿作成が不可能になります。業務の標準化なしに法令対応は成立しないという認識が必要です。
落とし穴4:荷主からの閲覧請求への準備不足
荷主が「どこの会社が運んでいるのか見せてほしい」と言ったとき、即座に提示できなければ信頼を失います。帳簿は「作って終わり」ではなく、「いつでも見せられる状態」が前提です。
落とし穴5:既存システムとの二重管理
運行管理システム・配車システムと帳簿が別管理になると、現場の入力負担が倍増し、形骸化します。既存業務フローとの統合設計が成否を分けます。
法令遵守を「競争優位」に変える3つの視点

今回の法改正は、単なる事務負担の増加ではありません。
むしろ、透明性を武器に信頼を獲得し、ビジネスチャンスに変える絶好の機会です。
視点1:荷主との価格交渉材料にする
「当社は実運送体制を完全に可視化しており、いつでも閲覧いただけます」
この一言が、荷主からの信頼獲得と適正運賃交渉の根拠になります。不透明な業者との差別化要素として、提案資料に盛り込むことも有効です。
視点2:協力会社との関係強化
管理簿を通じて協力会社の稼働実績を可視化することで、公平な評価・適切な配分が可能になります。「ちゃんと見てくれている」という安心感が、協力会社の定着率向上につながります。
視点3:内部統制・ガバナンス強化のアピール
金融機関への融資申請、M&A時のデューデリジェンス、大手荷主との新規取引審査――すべてにおいて「管理体制の透明性」は評価ポイントです。
管理簿の整備実績は、企業価値向上の証拠になります。
「規制」を「信用の可視化ツール」に変える

"実運送体制管理簿は「規制」ではなく、「信用を可視化するツール」である。"
経営者・管理者・現場担当者が一体となり、法令遵守と信頼向上を両立させることが、これからの時代の標準になります。
この記事が、貴社の実運送体制管理簿対応の第一歩となれば幸いです。
わからないことがあれば、専門家や業界団体にも積極的に相談し、「丸見えの時代」を生き抜く強い組織をつくっていきましょう。









