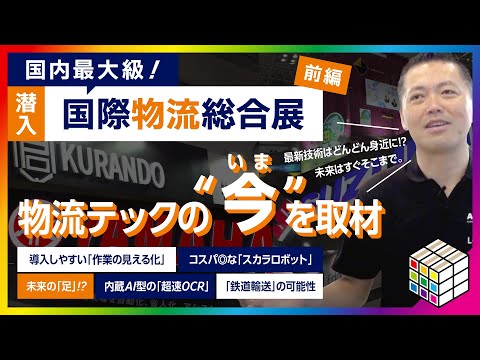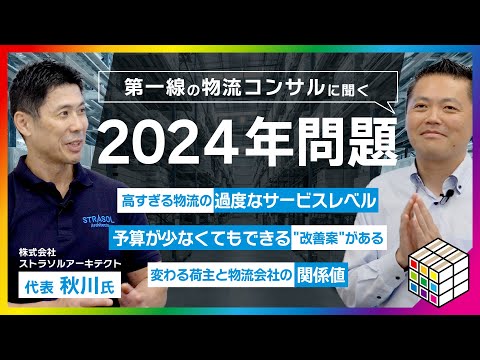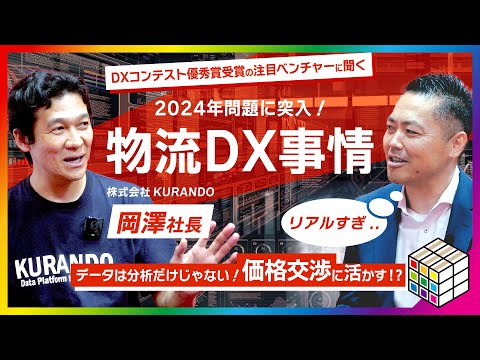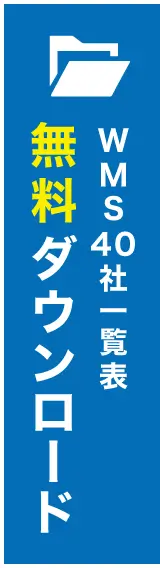改正貨物自動車運送事業法とは?企業が取るべき対応とェックリスト
目次

今回は改正貨物自動車運送事業法について解説します。国土交通省や経済産業省が発表した改正貨物自動車運送事業法をわかりやすくご紹介します。企業が取るべき対応のチェックリストもご用意したため、ぜひご利用ください。
2025年4月に改正貨物自動車運送事業法が施行され、物流事業者には新たな管理体制の整備や運送契約の明文化、安全管理の徹底が求められるようになりました。
今回の法改正は、慢性的なドライバー不足や多重下請構造の是正といった物流業界が抱える課題に対処するためのものです。
今回は改正貨物自動車運送事業法の全体像と実務ポイントをわかりやすく解説します。法改正に備える際にお役立てください。
改正貨物自動車運送事業法とは
改正貨物自動車運送事業法とは、物流業界の多重下請構造の是正やドライバーの労働環境の改善を目的とした法律です。
トラックドライバーの有効求人倍率は2倍を推移しており、他業種と比較しても高く、求人を出しても集まらない状況が続いています。
年々深刻化しているトラックドライバー不足が解消できなければ、輸送能力が低下すればモノが運べなくなり、国民生活や経済活動に多大な影響を及ぼします。そのため、トラックドライバーを魅力ある職業にしていくことが不可欠であり貨物自動車運送事業法が改正されました。トラックドライバーが働きやすくなるように、物流事業者には物流の取引条件や労働環境の見直しが求められます。
【トラック事業者向け】改正貨物自動車運送事業法の対応方法

改正貨物自動車運送事業法への対応として、トラック事業者は以下の点を見直す必要があります。多重下請構造の是正や不当な価格での契約を防止するために対応しましょう。
運送契約締結時の書面交付
改正貨物自動車運送事業法により、運送契約時の書面交付が義務化されました。ドライバーが契約外の作業を強いられるトラブルを防ぎ、適正な運賃・料金の収受ができるようにすることが目的です。
トラック事業者は、荷主や委託先と契約する際(※)には、運送内容・附帯業務・追加費用などを明記した書面を交付し、1年間保存する必要があります。
<記載事項>
- 荷役作業・附帯業務の内容と料金
- 特別費用(例:燃料サーチャージ、有料道路料など)
- 契約当事者の氏名・名称および住所
- 運賃・料金の支払方法
- 書面の交付年月日
(※)荷主と運送契約を締結する際は相互の書面交付、利用運送を行うときは委託先への書面交付が必要になります。
発注適正化(健全化措置)
改正貨物自動車運送事業法では、物流業界の多重下請構造の是正や不当な価格での契約を防止するために、元請事業者が利用運送を行う際に委託先への発注を適正化することが努力義務として課されました。この取り組みは「健全化措置」と呼ばれ、具体的には次のような内容が含まれます。
(1)委託前に運送費用の概算額を聞いて発注する
(2)荷主の提示額が適正価格を下回る場合は、委託先は価格交渉できる
(3)再委託が予想される場合は、委託先に再々委託の制限など条件を提示する
参考資料:「改正貨物自動車運送事業法の施行について」(国土交通省)
運送利用管理規程の作成と管理者の選任
前年度の利用運送量が100万トン以上の事業者に対し「運送利用管理規程の作成」と「運送利用管理者の選任」が義務付けられます。対象事業者は毎年提出する「事業実績報告書」の利用運送量で判断され、該当事業者は翌年度の7月10日までに国土交通大臣へ届け出なければなりません。
運送利用管理規程には「健全化措置の運営方針」「健全化措置の内容」「管理体制の構築」「運送利用管理者の専任」を記載します。国土交通省の「運送利用管理規定(例)」を使用すると簡単に作成できます。運送利用管理者は役員など管理職から1名選びましょう。
実運送体制管理簿の作成と情報通知
1.5トン以上の貨物を取り扱う元請事業者に対して、実運送体制管理簿の作成が義務付けられました。
実運送体制管理簿とは、委託先となる実運送事業者の情報を明確に記載し、多重下請構造の見える化と取引の透明化を図るためのものです。下請事業者から必要な情報を教えてもらい管理簿を作成して1年間保存します。
【軽トラック事業者向け】改正貨物自動車運送事業法の対応方法

改正貨物自動車運送事業法において、軽トラック事業者には次の見直しが求められます。
貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車運送事業者は、安全管理者の選任と講習受講が義務化されました。安全管理者の選任と選任後は2年ごとに定期講習を受講する必要があり、未受講の場合は法令違反となる恐れがあります。独立行政法人自動車事故対策機構で3,700円で講習が受けられます。
| 項目 | 初任講習(選任時) | 定期講習(選任後2年ごと) |
| タイミング | 選任時 | 選任後2年ごと |
| 目的 | 安全確保に関する業務に必要な基礎知識の習得 | 最新の制度・安全対策に基づく管理知識の更新 |
| 所要時間 | 合計5時間以上 | 合計2時間以上 |
| 主な講義内容 | ・関連法令(自動車運送事業法等) ・安全運転指導・運行管理 ・過積載・荷崩れ防止 ・労務・健康管理など | ・最新の制度・行政指導内容 ・安全対策の実務例 ・重大事故の傾向と再発防止策など |
| 受講義務者 | 貨物軽自動車運送事業の安全管理者に選任された者 | 初任講習受講者 |
貨物軽自動車安全管理者の選任
営業所毎に1名の安全管理者を選任することが義務付けられています。物軽自動車安全管理者は運転者に対する指導や監督、業務や事故の記録などの業務を行います。同一人物による複数営業所の兼任は原則禁止です。
<貨物軽自動車安全管理者の要件>
- 貨物軽自動車安全管理者講習を修了した日から2年以内の者
- 選任予定日より前2年以内に定期講習を修了している者
- 一般貨物自動車運送事業等において安全管理業務に従事した経験がある者
貨物軽自動車安全管理者の届出
<
安全管理者を選任した際に、遅滞なく運輸支局などへ届出を行うことが義務となっています。届出の不備や遅延は指導・是正勧告の対象になるため、選任後すぐに提出しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 届出が必要な情報 | ・事業者の氏名・名称・住所 ・安全管理者の氏名・生年月日 ・選任日 ・営業所の名称・所在地 |
| 届出様式 | 国土交通省の様式(HPで公開)を使用 ※地域ごとに異なる場合は指示に従う |
| 添付書類 | ・講習修了証の写し ・修了予定を証明する書類 ・安全管理業務経験の確認書類(該当者のみ) |
| 届出先 | 営業所を管轄する運輸支局・陸運支局 |
| 届出のタイミング | 安全管理者の選任後、速やかに届出 |
| 届出の方法 | 紙で提出(電子届出システムは準備中)[花芦9] |
初任・高齢・事故歴運転者への安全指導
<
交通事故の未然防止を目的として、一定の条件に該当する運転者に対し特別な安全指導を実施し「貨物軽自動車運転者台帳」に記録・保存する義務があります。これらの特別指導を怠ると法令違反になる可能性があります。
<指導時間>
- 初任運転者・事故惹起者:合計5時間以上
- 高齢運転者:1時間以上(適正診断の結果を伝えて安全な運転を考えさせる)
運転者への適性診断
運転者の運転傾向や注意力などを把握し、安全運転に資するため、一定の運転者に対して適性診断の受診が義務付けられています。診断結果は運転者台帳に記録し、社内での指導に活用します。
各地の認定適性診断機関で受診してもらい、診断結果は貨物軽自動車運転者台帳に記録・保存しましょう。
定期的な健康診断
<
運転者に対して年1回以上の健康診断を実施する義務があります。安全運転を確保するためには、身体面・精神面の両面から健康状態を常に把握することが大切です。
<身体面の診断>
- 病気の兆候がある場合は早期に医師の診察
- 健康診断で指摘をされた場合は、適切な治療を行う
- 労働安全衛生法に基づき健康診断を受診
<精神面の診断>
- 心身の余裕を持たせる配慮(リフレッシュ休暇等)
- 厚生労働省のメンタルサポートを活用する
運転者への指導・監督
安全運転者に対して年1回以上、安全運転のための技術指導および法令遵守事項の指導・監督を実施する義務があります。実施内容・日時・対象者を記録します。これは事故防止と安全管理体制の強化を目的としたものです。
<指導・監督の内容>
- 車両点検と事故発生時の対応方法
- 健康状態・運転姿勢・労務管理の重要性
- 運転時の危険予測と安全確保
- 法令改正への対応と社会的責任
- 危険物・特定車両等の取り扱いと安全措置など
点呼
運転者の運行開始・終了時に点呼(報告・確認)を実施する義務があります。点呼実施内容は記録し、1年間保存します。これは安全運行の最終チェックとして位置づけられており、異常があれば運行を中止する判断が必要です。
■ 実施方法・確認内容
- 酒気帯びの有無(アルコール検知器使用が原則)
- 疾病・疲労・睡眠不足の兆候確認
- 体調・顔色・声の調子等を目視・聴覚でチェック
- 車両の点検状況、道路・気象・交通情報の把握
運転者の勤務時間の遵守
運転者の勤務時間・休息・拘束時間の上限を守る義務があります。基準を超える労働は過労運転や事故の要因となるため、事前の業務計画と記録の確認が不可欠です。拘束・運転・休憩時間を把握しておきましょう。
| 項目 | 基準内容 |
| 年・月の拘束時間 | 年3,300時間以内 月284時間以内 |
| 1日の拘束時間 | 原則13時間以内 (上限15時間、14時間超は週2回までが目安) |
| 運転時間の上限 | 原則2日間で9時間以内、2週間で44時間以内 |
| 休息時間 | 11時間以上与えるように努めて9時間を下回らない |
| 連続運転時の休憩 | 4時間超の連続運転では、途中で30分以上(10分以上×複数回でも可)の休憩が必要 |
異常気象時の安全確保措置
大雨・大雪・暴風などの異常気象により輸送の安全が脅かされる恐れがある場合、適切な判断と安全措置の実施が義務付けられています。気象警報が発令された時点で、運行の可否を速やかに検討し、必要に応じて中止や経路変更などの措置を講じなければなりません。
運行管理者は出発前に最新の道路・気象情報を確認し、業務の開始や継続の判断を下す必要があります。場合によっては、営業所への待機指示や迂回路の設定、運転中止の決定も視野に入れ、安全を最優先にした運行管理が求められます。
運転者の日報作成
運転者ごとに業務の開始・終了時刻、経由地、休憩、異常の有無などを記録する義務があります。これは一般的に「日報」とも呼ばれ、記録漏れや記載ミスがあると法令違反となる可能性があります。
業務が完了するたびに日報を作成することが基本であり、休憩時間や積み下ろし地点など業務中のあらゆる行動について記録を残す必要があります。記録は書面または電磁的な方法で行い、最低でも1年間は保存しなければなりません。
過積載の防止
貨物軽自動車運送事業者にとって、過積載は重大事故や車両トラブルを招く危険行為であり、法令違反として厳しく取り締まられる対象です。
最大積載量を超えて運行することは、安全性を損なうだけでなく、事業停止や罰則といった行政処分のリスクも伴います。そのため、積載前には貨物の重量を正確に把握し、必要に応じて計量や再積載を行うことが求められます。特に、複数拠点からの積載や荷主からの追加指示がある場合でも、法令遵守を最優先とする判断が不可欠です。
過積載を防ぐことは、安全運行の前提であり、事業者としての社会的信頼にも直結します。日常的な運行管理と社内教育を通じて、トラックドライバーへの意識付けを徹底しましょう。
事故発生時の記録
貨物軽自動車運送事業者は、物損事故を含むすべての事故が発生した際に、その概要・発生状況・原因・再発防止策などを正確に記録し、営業所単位で保存する義務があります。これは、事故原因の把握と再発防止に向けた社内対策の根拠となるものであり、事後対応の信頼性を高めるためにも欠かせない業務です。
記録には、事故を起こした運転者の氏名、車両番号、発生日時・場所、関係者の情報、事故の種類や損害の状況、そして事故後に講じた対応内容や再発防止策まで含める必要があります。これらの情報は、書面または電磁的な方法により3年間の保存が義務付けられています。
国土交通大臣へ重大事故の報告
貨物軽自動車運送事業者は、死亡事故や重傷事故などが発生した場合、30日以内に国土交通大臣宛ての事故報告書を提出する義務があります。加えて、5人以上の死傷や10人以上の軽傷者が発生した重大事故では、24時間以内に運輸支局等へ速やかに通報しなければなりません。
事故の日時・場所、被害の状況、原因、再発防止策などを含め、書面または電子的な方法で提出します。報告先は、営業所を管轄する運輸支局や陸運事務所です。
重大事故の報告は、迅速かつ正確な対応が求められるため、社内での対応マニュアル整備と連絡体制の明確化が不可欠です。あらかじめ役割分担を決め、緊急時に迷わず対応できる体制を整えておきましょう。
チェックリストで確認する対応漏れの防止
改正貨物自動車運送事業法に対応するためのチェックリストを作成したため、ぜひご利用ください。
| 対象事業者 | チェックリスト |
| トラック事業者 | 運送契約締結時の書面交付 |
| 発注適正化 | |
| 運送利用管理規程の作成 (前年度の利用運送量が100万トン以上) | |
| 運送利用管理者の選任 (前年度の利用運送量が100万トン以上) | |
| 実運送体制管理簿の作成 (取扱貨物量1.5トン以上) | |
| 軽トラック事業者 | 貨物軽自動車安全管理者の講習受講 |
| 貨物軽自動車安全管理者の選任 | |
| 貨物軽自動車安全管理者の届出 | |
| 初任・高齢・事故歴運転者への安全指導 | |
| 運転者への適性診断 | |
| 定期的な健康診断 | |
| 運転者への指導・監督 | |
| 点呼 | |
| 運転者の勤務時間の遵守 | |
| 異常気象時の安全確保措置 | |
| 運転者の日報作成 | |
| 事故発生時の記録 | |
| 国土交通大臣へ重大事故の報告 |
まとめ
今回の法改正により、契約書面の交付や管理簿の整備、安全指導や健康診断など、事業者の実務負担は増加します。しかし、これらはドライバーの労働環境を改善し、持続可能な物流を実現するために不可欠な取り組みです。
各事業者は対応漏れがないよう社内体制を整備し、管理者の選任・記録の保存・講習の受講といった義務を確実に履行していく必要があります。ぜひチェックリストを活用して備えてみてください。