
各種ホワイトペーパー
無料ダウンロード
目次
2025年、トラック運送業界を揺るがす二つの法改正が相次いで打ち出されました。
4月には、運送事業者に対する管理体制の強化を柱とした制度が施行され、さらに6月には、荷主や元請の責任を明文化する追加の法改正が成立。取引構造全体にメスを入れる内容として注目を集めています。
いずれも、ドライバー不足や価格競争の激化、責任分散によるリスク拡大といった業界が抱える構造的課題に対応するための措置です。制度の本格的な施行を前に、現場では契約実務や管理体制の見直しが急務となっています。
| 制度項目 | 2025/4 施行 | 2025/6 成立 | 2026〜28 施行予定* |
|---|---|---|---|
| 許可更新制 | 取り消しがない限り有効 | 5年ごとの許可更新制へ | 2028年度目途 |
| 最低運賃 | 標準的運賃は努力目標 | 適正原価に基づく最低運賃を告示、下回る設定は禁止 | 2027年度目途 |
| 二次下請け努力義務 | 2次下請けまでに留める努力義務 | 引き続き2次下請けまでの努力義務を明文化 | 2026年度監視強化 |
| 白トラ罰則(荷主) | 行政指導中心 | 荷主に対し最大100万円の罰則、白トラ委託を禁止 | 2026年度施行 |
| ドライバー処遇義務 | ― | 処遇改善(評価・賃金)の努力義務を法文化 | 2027年度指標公表 |
| 真荷主責任 | 第一種利用運送事業者経由は除外される構造 | 真荷主の定義を拡大(利用運送事業者経由も含む) | 2026年度段階導入 |
※政令・省令で細部調整中のため、年度は目安です。
本記事では、この二段階の制度変更で押さえておくべき6つのポイントを取り上げ、実務に与える影響と今後求められる対応について、現場目線で整理します。
※この記事の内容は公開時点(2025 年 7 月)の情報に基づきます。
1. 許可の更新制度が導入される方向に
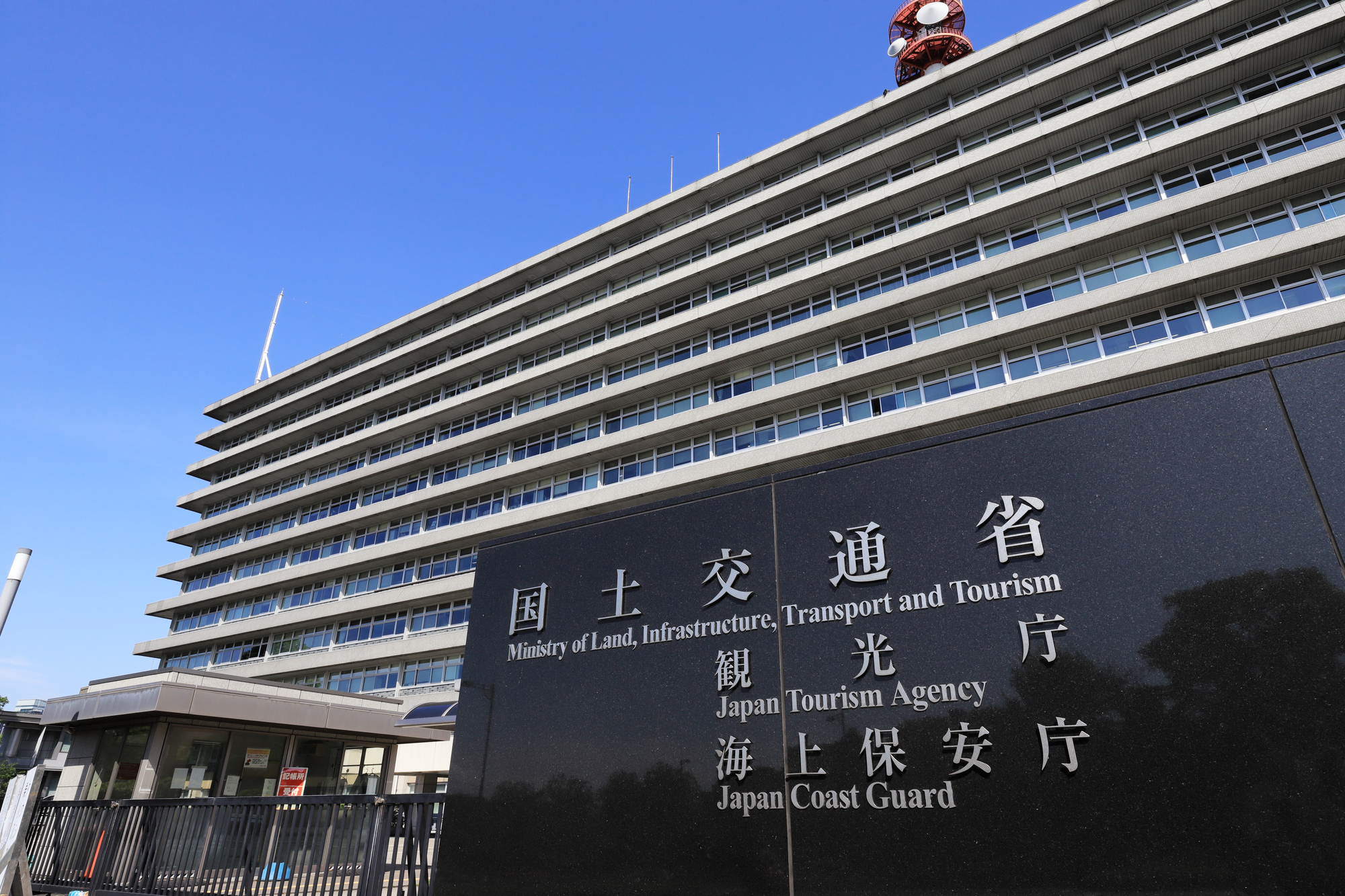
これまで、運送事業者に与えられる事業許可は「無期限」が原則でした。一度取得すれば、その後に継続的なチェックを受けることなく、形式的には永続的に事業を続けられるというのが、長らく業界の実態でした。
しかし、こうした制度は、運行管理や労務体制が十分でないまま事業が継続されてしまう温床でもありました。事故や違反が起きるまで行政のチェックが及ばないという構造的な課題が、以前から指摘されていたのです。
こうした背景を踏まえ、事業許可の更新制度が導入される方向で検討が進められています。新たな制度では、5年ごとに法令順守や業務管理体制について審査を受け、条件を満たさなければ許可が更新されない仕組みへと変わっていく見込みです。
その際に問われるのは、運行記録や勤怠管理、財務状況といった帳簿類の“形式”だけではなく、そうした運用が実態としてきちんと機能しているかどうかです。
ちょうどそのような流れを世に印象づけるきっかけとなったのが、2025年6月に報じられた日本郵便の事例です。全国の拠点において乗務前点呼の未実施や記録の不備が判明し、同社は国土交通省から5年間の許可取消し処分を受けました。
法改正とは直接の因果はないものの、管理体制の不備が企業規模にかかわらず厳しく問われるという現実を、多くの事業者が実感する契機となりました。
今後は、記録があるかどうかではなく、その中身と運用実態が一致しているかが審査対象となります。許可の取得や維持に向けて、書類を整えるだけでなく、現場オペレーションと制度の整合性を高めていく必要があります。
許可更新制は、企業のガバナンス体制や日々の業務品質を可視化し、外部の目で評価する仕組みです。求められるのは、単なるルール整備ではなく、実務の中で“仕組みとして回る管理”を築くことです。
現場の声や実態をもとに、改めて「継続可能な体制とは何か」を具体的に考え直す必要があります。
2. 最低運賃制度の創設へ

これまで、トラック輸送における運賃設定は市場任せの構造が続いていました。国が定める「標準的運賃」は存在していたものの、その適用はあくまで任意であり、拘束力のない“参考水準”にとどまっていました。
その結果、荷主側が価格交渉力を強く持ち、運送事業者側はコスト割れすれすれの運賃で受託せざるを得ないケースも珍しくありませんでした。とくに中小規模の事業者ほど、安値受注を繰り返す中で、ドライバーの長時間労働や車両整備の先送りといった問題が慢性化していたのが実情です。
こうした取引慣行にメスを入れる施策として、「最低運賃制度」の導入が予定されています。これは、適正原価に基づいて一定の下限運賃を国が定め、それを下回る契約を法律違反とみなす制度です。
荷主・元請との契約段階においても、この下限を守らなければならず、違反時には行政処分の対象となります。形式的には合法でも、実質的に下限割れとなる価格設定は、今後厳しく制限されていくことになります。
この制度の背景には、運送コストを物流事業者の内部努力だけで吸収させるのではなく、荷主も含めた業界構造全体で適正化を図ろうとする国の方針があります。適正な運賃収受がなされなければ、ドライバーの処遇改善も、安全管理への投資も、現実的には成り立ちません。制度は、その前提を支えるためのものです。
その一方で、最低運賃が制度として明示されるとはいえ、実務の現場では運賃交渉の中で「自社の条件に即した根拠を示す力」も重要になってきます。
制度上は一律の下限が定められるとはいえ、業種や地域、荷姿、積載率などの違いによって、各社が必要とするコスト構造は大きく異なるためです。
最低運賃を下回らないことは法的義務となりますが、それ以上の水準で適正な取引条件を実現するには、「なぜその価格なのか」を明示できる積算力や資料整備が、交渉の現場で必要とされる場面も多くなるでしょう。
| 区分 | 構成比の目安 |
|---|---|
| 人件費(運転・配車) | 60 % |
| 車両償却・維持 | 25 % |
| 保険・高速・燃料調整 | 10 % |
| 管理間接経費 | 5 % |
🟩 人件費(60%)
🟦 車両償却・維持(25%)
🟧 保険・高速など(10%)
⬜ 管理間接経費(5%)
※上記は平均的な一般貨物のイメージ。自社計算では積載率・待機率・走行距離などを変数に再積算することが必須となります。
適正な原価意識が業界全体に定着していけば、単なる価格競争から脱却し、サービス品質や柔軟性といった「提供価値」で選ばれる市場への転換も期待できます。
その意味で、最低運賃制度は単なる規制措置ではなく、物流事業者がその専門性や強みをきちんと評価される環境づくりの土台にもなり得るのです。
3. 再委託は原則「二次まで」に制限されるようになる

輸送の現場では、元請が受けた業務を複数段階で再委託する、多重下請け構造が常態化していました。
しかし、委託が重層化することで責任の所在が不明瞭になり、労務管理や契約内容の実態把握が難しくなるなど、リスクが大きくなるのも事実です。とくに三次請け以降では、ドライバーの労働条件や運賃水準の適正性が担保されにくくなっていました。
こうした課題を受けて、法改正では再委託に関するルールが強化されました。従来は「再委託は原則として二次までとする努力義務」にとどまっていましたが、今回の改正ではその内容が制度上に明記され、行政が監視・是正に介入しやすい枠組みへと移行しました。
努力義務という位置づけ自体は変わらないものの、その法的な扱いが明文化されたことで、実務上の重みは大きく変わったと言えます。
この改正を機に、元請は下請けルートの把握と管理体制の整備が求められるようになります。とくに再委託先がさらに再委託していないか、適切な運賃・労務管理がなされているかといった点は、今後厳しく問われることになるでしょう。
荷主にとっても、契約書の中で再委託範囲を定める、あるいは調達方針として「再委託の可視化」を盛り込むなどの対応が必要になります。
委託ルートを追える状態を維持することは、コンプライアンス対策としても重要です。
複層的な下請け構造の中で「誰が輸送を担っているのか」が見えにくくなることは、トラブル発生時の対応遅れや、労働環境の見えないブラックボックス化を招きかねません。
今回の法改正は、そうした構造的なリスクを見直すきっかけとして、実効性ある管理の第一歩となるはずです。
4. 白トラ行為への罰則強化

いわゆる「白トラ」とは、運送業の許可を持たない事業者が貨物運送を有償で請け負う、違法な営業行為を指します。車両は営業ナンバー(緑ナンバー)ではなく、自家用(白ナンバー)のまま運行されるため、法的な監視対象外となり、安全性や労働環境の面でも重大なリスクをはらんでいます。
こうした白トラ行為については、これまで行政指導や是正勧告にとどまり、荷主が依頼しても罰則はほとんどありませんでした。
しかし今回の法改正では、無許可運送を依頼した荷主に対しても罰則を科す新たな規定が導入され、最大で100万円の過料が課されることになります。
| 主体/行為 | 無許可運送を行う | 依頼する | 黙認する |
|---|---|---|---|
| 無許可業者 | 罰則(従来通り) | ― | ― |
| 元請事業者 | ― | 行政指導〜処分 | 行政指導 |
| 荷主 | ― | 過料 最大100万円 | 行政指導 |
これは「知らなかった」では済まされない制度への転換です。荷主側には、運送を委託する際に相手先の許可証を確認し、契約書面を整備するなど、適法性を確認する義務が実質的に課されることになります。
また、元請事業者が白トラ業者を仲介していた場合も、荷主の責任が問われる可能性があります。調達フローに潜むリスクを棚卸しし、委託ルートの透明化を図ることが、今後の実務では欠かせません。
行政は、白トラ対策を“物流業界の健全化の起点”と位置づけています。形式的な契約の有無だけでなく、実質的な運送実態がどうなっているかを含めて問われる時代に入ったと言えるでしょう。
5. ドライバー処遇の明文化

ドライバーの労働環境は、長時間労働や低賃金、休憩時間の確保困難といった課題を長年抱えてきました。特に2024年問題による時間外労働の上限規制を契機に、その実態が社会的にも注目を集めるようになっています。
今回の法改正では、こうした背景を受けて、運送事業者に対してドライバーの処遇確保を「義務」として明文化する措置が導入されました。従業員の待遇を確保する努力が、単なる経営判断ではなく、法的責任として位置づけられることになります。
具体的な指標や水準は政省令等で定められる見通しですが、賃金の適正化、拘束時間の短縮、安全教育の実施などがチェック対象になると考えられます。制度の具体化に先立ち、各社には自社の労務実態を把握し、是正が必要な領域を可視化することが求められます。
ドライバーの処遇改善は、単に法令順守のための対応にとどまらず、人材確保や定着率向上の観点からも不可欠です。制度施行後には、外部からの監査や更新審査の対象にもなる可能性が高く、早期の準備が重要です。
6. 真荷主責任の拡大

これまでの制度では、運送契約の当事者にあたる第一種利用運送事業者を通じて手配が行われた場合、実際の荷主が直接の責任を問われることはほとんどありませんでした。形式的には契約外の第三者と見なされ、法的な義務や罰則の適用対象から外れることが多かったのです。
しかし今回の法改正では、たとえ利用運送事業者を介した委託であっても、実質的に荷主としての役割を果たしていれば、その責任を負うという考え方が明確に打ち出されました。
いわゆる“真荷主責任”の拡大です。
これにより、実際に運送を指示していた者、条件を決定していた者、実運送の管理を実質的に握っていた者が、形式上の契約関係にかかわらず、規制の対象となります。
とくに白トラ行為の関与や、違法な再委託構造への黙認といったケースでは、「関係していたかどうか」ではなく、「関与を否定できる体制があったか」が問われることになります。
この考え方は、荷主企業にとって調達・委託体制全体の見直しを迫るものです。発注時の経路や条件設定、管理責任の所在をあらかじめ整理し、契約書や社内手続きを通じて実態と整合性を持たせることが、リスク管理上ますます重要になります。
まとめ

| 許可更新 | 最低運賃 | 二次下請け | 白トラ罰則 | 処遇義務 | 真荷主責任 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運送事業者 | ◎ 審査対象 |
◎ 遵守 |
◎ 監視 |
△ 元請仲介時リスク |
◎ | ― |
| 元請 (利用運送) |
― | △ 適正運賃提示 |
◎ 管理義務 |
△ 仲介責任 |
△ | ◎ 実質荷主の場合 |
| 荷主 | ― | ◎ 支払い義務 |
△ 再委託可視化 |
◎ 過料対象 |
△ | ◎ 適用拡大 |
◎=直接義務 / △=連動責任 / ―=対象外
2025年4月に施行された改正と、同年6月に成立したさらなる改正内容は、それぞれ独立した制度変更ではなく、段階的に連動する構造になっています。前者で運送事業者の管理体制強化が進められ、後者では荷主・元請にも責任を広げることで、業界全体を底上げする狙いがあります。
許可制度の見直しや最低運賃の導入、再委託の制限強化、白トラ対策、ドライバー処遇の義務化、そして真荷主責任の拡大といった一連の改正は、それぞれが個別のテーマでありながら、共通して「健全な取引関係と責任の明確化」を柱としています。
今後、各制度が施行された際に問われるのは、単なる帳簿や契約書の整備ではなく、「実態としてどう管理・運用されているか」という現場レベルでの体制構築です。
形式的に適法であっても、実態が伴っていなければ行政指導や更新拒否の対象となり得る時代に入っています。
すでに制度の一部は施行されており、残る法改正も近い将来の実施が見込まれています。制度への対応を待つのではなく、今の段階から各社が実務の棚卸しを行い、段階的に体制を整えていくことが求められます。
業界全体としての健全化の波に、受け身ではなく能動的に向き合う姿勢こそが、これからの運送ビジネスの持続性を支える鍵となるはずです。








